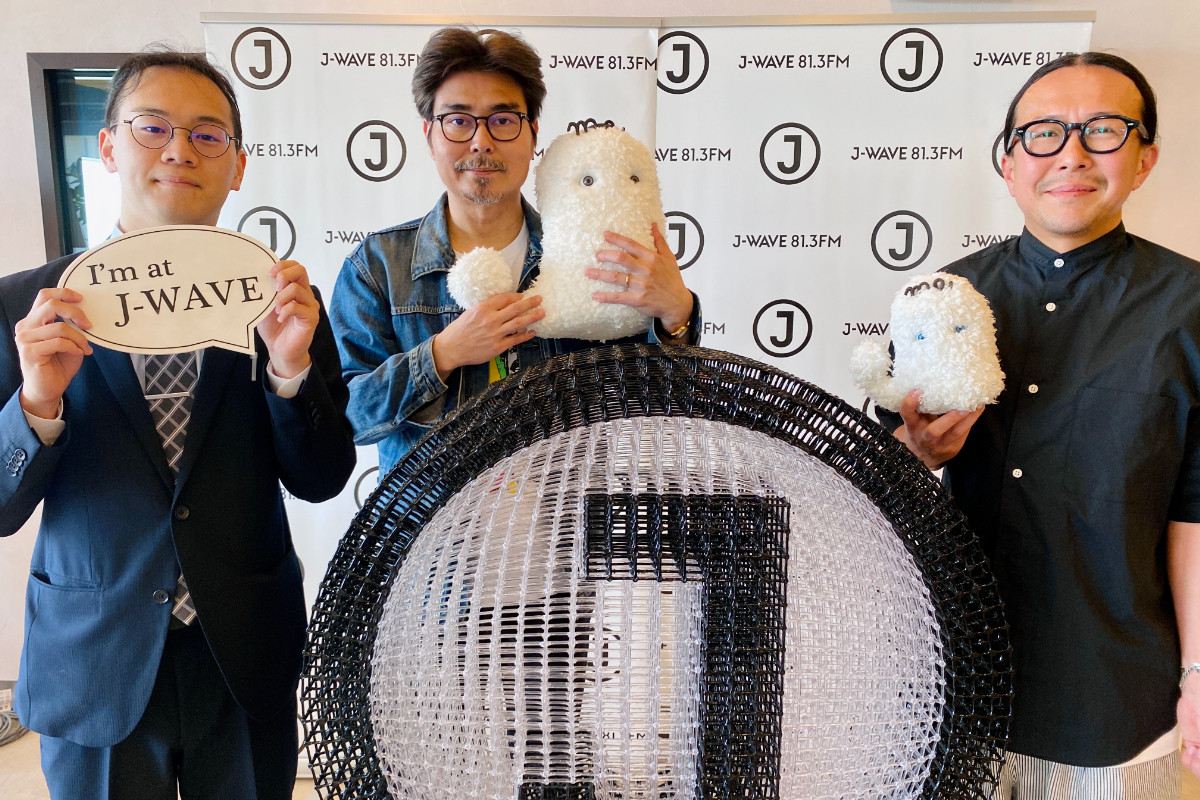寝たきりでも遠隔操作によりカフェで働ける分身ロボット「OriHime」を開発したロボット研究者で株式会社オリィ研究所の所長・吉藤オリィさんが、ロボット開発に目覚めたきっかけや「OriHime」を発明するまでの紆余曲折、さらには、最近開始した画期的な新サービスなどについて語った。
吉藤さんは1987年奈良県生まれ。自身の不登校の体験をもとに「孤独の解消」を目的として「OriHime」を開発し、障がい者雇用を創出する人物だ。
吉藤さんが登場したのは、俳優の小澤征悦がナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組『BMW FREUDE FOR LIFE』(毎週土曜 11:00-11:30)。同番組は、新しい時代を切り開き駆け抜けていく人物を毎回ゲストに招き、BMWでの車中インタビューを通して、これまでの軌跡や今後の展望に迫るプログラムだ。
・ポッドキャストページ
吉藤さんは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や頸椎損傷などで寝たきりになった人たちの「もう一つの肉体」となる遠隔操作可能な分身ロボット「OriHime」を手掛けるロボット研究者だ。さぞ幼少期からロボットに強い関心を持ち、機械いじりに熱中していたのかと思いきや、そんなこともないようだ。
吉藤:私は昔からロボットが好きだったわけではありません。一番得意だったのは折り紙です。私には病気療養などの理由で3年半ほど不登校だった時期があります。学校に居場所がなく、天井ばかりを眺め続ける孤独で辛い日々でした。当時の唯一の趣味が折り紙で。朝から晩まで14時間ずっと折り続けたこともありました。その様子を心配した母親が「折り紙を折れるんだったら、ロボットを作れるに違いない」と考え、私が中学1年生のときにロボットコンテストに申し込んでくれたんです。言われるままに出場したところ、はじめてプログラミングを経験したのですが、運よく優勝することができました。

吉藤:ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊教授が名誉アドバイザーを務められた「JSEC」に出場した私たちは、「傾かない車いす」を作りました。自動車で車道から歩道に移動する際、車体が傾きますよね。そこで傾かずに段差を上がれるよう、改造したタイヤ・ホイールを備えた車いすを発明したんです。この車いすを見た小柴先生に「君は研究者に向いているよ。もっと研究したらいい」と言っていただきました。その会場が日本科学未来館でした。私にとって、様々な教授にお会いし、後に早稲田大学に進学するきっかけを作ってくれた場所でもあります。
 その後、私たちの発明した車いすに実際に障がいをお持ちの方々に乗っていただき、コメントをもらっているうちに、車いすだけではどうしても行くことができない場所が存在すると気付きました。また、健常者であれば1時間で行けるところを、車いすではその倍の時間かかる場合もある。中には病院から出られない人だっている。その方たちが社会に参加するためには、車いすだけでは限界があると感じたんです。そこで「心を運ぶ車いす」を作ることができないだろうか?となり、「もう一つの身体」があればいいのにと思うようになりました。
その後、私たちの発明した車いすに実際に障がいをお持ちの方々に乗っていただき、コメントをもらっているうちに、車いすだけではどうしても行くことができない場所が存在すると気付きました。また、健常者であれば1時間で行けるところを、車いすではその倍の時間かかる場合もある。中には病院から出られない人だっている。その方たちが社会に参加するためには、車いすだけでは限界があると感じたんです。そこで「心を運ぶ車いす」を作ることができないだろうか?となり、「もう一つの身体」があればいいのにと思うようになりました。
吉藤:私は高校時代、車椅子でも移動が難しい人が孤独を解消できるよう、人工知能の友達ロボットを作ろうと考えました。人と話すことが苦手だけど、気を遣いたくなくて、でも寂しいという人が行き着く先って、往々にして人工知能の友達を作ることだったりするのですが、私もその例に漏れなかったわけです。ところが、1年ほど開発に取り組んだところで「虚しい」と思うようになってしまいました。私がロボットコンテストへの出場をきっかけに不登校から復帰できたように、人生が変わる瞬間は「人との出会い」によって形作られていくものだと思います。しかし、移動困難な人はその機会を得ることができない人生を歩んでいる。後に出会った寝たきりの親友は「移動できない最大のハンディキャップは、人生に出会いと発見がないことなんだ」と言っていました。だとしたら、彼らが人生の中で出会いを得られる状況を作るアプローチをしていくべきだと考え、人工知能の開発をやめたんです。
人工知能開発を諦めた吉藤さんが次に着目したのはVRだ。現実世界からVR=仮想現実の世界へアクセスするには、ゴーグル型のディスプレイ「ヘッドマウントディスプレイ」を頭に装着する必要がある。仮想空間上では、性別や見た目を変えることができ、身体的なハンディキャップもなく自由に動き回ることが可能だ。吉藤さんは「寝たきりで身体を動かせない人たちにとって、オンライン世界はもはやリアル。そういった人がリアルへダイブするための『逆ヘッドディスプレイ』を作れないだろうか」と発想し、OriHimeを開発したという。
吉藤:早稲田大学在学中に参加したJSEC歴代優勝者が集まる交流会で、私の2大会後に優勝した結城さんという女性と出会いました。OriHimeを開発したばかりの私は進路に悩んでいたのですが、ロンドン大学でビジネスを学んだ経験のある彼女から「これビジネスにしなよ」と勧められたんです。当時の私はビジネスのビの字も知らず「あまり興味ないな」と答えました。すると結城さんは「バカ野郎」と。「吉藤が本当にやりたいことは『孤独の解消』のはず。であれば、孤独を解消された世界をちゃんとイメージしなければダメだよ」と怒られたんです。さらに、「身体が弱い吉藤がもしも早くに亡くなったとしたら、分身ロボットのメンテナンスをする人がいなくなり、サービス自体が終了してしまう。それではプロジェクトが自立していない」と指摘された上で、「単に分身ロボットを作りたいだけなのか、それとも、自分がいなくなった後も維持される社会の仕組みを作りたいのか」と問われたんです。私は「確かに」と納得しました。この分身ロボットのサービスを維持する方法として、結城さんはビジネス化を提案してくれたわけです。以降、結城さんと一緒にビジネスの勉強をし、計画書を書き、ビジネスコンテストに参加するなどして、少しずつビジネスとしての形を作っていきました。
こうして吉藤さんは2012年、結城さんらとともに株式会社オリィ研究所を設立。現在、同社の事業としてOriHimeが働く「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」を運営しており、お客さんからの反応は上々だという。その人気の理由とは?
吉藤:分身ロボットカフェで分身ロボットを遠隔操作する「パイロット」を務めてくださっている方は現在、全国に90名ほどいます。メニューを配膳し、オーダーを取ることはもちろん、コーヒーを作るバリスタロボットもいたりします。普通のカフェとの違いは、ロボットの店員さんがよくしゃべることです。普通のカフェだったら店員さんがずっと話しかけてきたらちょっと嫌じゃないですか。でも、ロボットカフェでは分身ロボットがずっとお客さんのそばにいて、30~40分ぐらいしゃべり続けていることが逆にウケているんです。パイロットのメンバーたちもOriHimeを介してであれば緊張せずに話せるみたいです。また、お客様もロボットの中の人に「どこに住んでいるんですか?」「前職は何をされていたんですか?」などと積極的にコミュニケーションを取られているようです。このように、分身ロボットにより自然とお互いが自己開示できる状態を作れることは一つ面白い発見でした。OriHimeは「心の車いす」でありながら、コミュニケーション能力を増幅してくれるツールとしても機能しているんです。


吉藤:分身ロボットが街を走行することは技術的には可能です。ただ道交法が厳しく、現状では日本橋のお店からOriHimeは出ることができません。街を自由に移動できるようになれば、お客様をガイドすることや、ウィンドウショッピングを楽しむこともできるかもしれない。そんなふうに将来的には、街の中で車いすの方と同じように心の車いすが走れる状態を作りたいと考えています。ただ、今あえてロボットの姿で自走する必要はないとも思っていて。分身なのだから小さくてもいいわけですね。なので最近開発した小さいOriHimeを海外の方の肩に乗せて、通訳やガイドをするという新しいサービスを実験的に展開しています。家から出ることができないけど、英語と日本語を話せてガイドができるという方がパイロットを務めているのですが、これは「肩乗りOriHime」と呼んでいます。ちょうど『ゲゲゲの鬼太郎』に出てくる目玉おやじのイメージですね。
孤独の解消された社会を実現するべく、OriHimeの持つ可能性を拡張し続ける吉藤さん。最後に彼にとっての挑戦、そしてその先にあるFreude=喜びとは何かと尋ねると、こんな答えが返ってきた。
吉藤:私は身体が弱く、昔から様々な機会を逃してきました。この状態がさらに悪化し、いつか家から出られなくなるかもしれないとずっと恐れています。だからこそ、分身ロボットによりベッドから社会参加し続けられる未来を実現させたいと考え、活動しています。よく「障がい者雇用を行っているいい人」と言われがちなんですけど、私はいい人でもないし、いいことがやりたいわけでもありません。私は孤独を解消することで「寝たきりの先」を作りたいのです。そのために、寝たきりの先輩たちに協力してもらい、研究をしているわけです。なので、将来は自分の身体を自分で介護していきたい。誰かに付きっきりで横にいてもらうのではなく、もう一つの身体を使って水を飲んだり、寝返りをサポートさせたり、服を着替えたりと、身体が全く動かなくても、自分で自分のことができるようにしていきたいんです。その状態を10年以内には実現させたいと思っています。
(構成=小島浩平)
吉藤さんは1987年奈良県生まれ。自身の不登校の体験をもとに「孤独の解消」を目的として「OriHime」を開発し、障がい者雇用を創出する人物だ。
吉藤さんが登場したのは、俳優の小澤征悦がナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組『BMW FREUDE FOR LIFE』(毎週土曜 11:00-11:30)。同番組は、新しい時代を切り開き駆け抜けていく人物を毎回ゲストに招き、BMWでの車中インタビューを通して、これまでの軌跡や今後の展望に迫るプログラムだ。
・ポッドキャストページ
ロボットではなく、折り紙に夢中だった少年時代
吉藤さんを乗せた「BMW i5 eDrive40 Touring M Sport」は、東京・お台場の国立科学館「日本科学未来館」を目指し、六本木ヒルズを出発した。吉藤さんは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や頸椎損傷などで寝たきりになった人たちの「もう一つの肉体」となる遠隔操作可能な分身ロボット「OriHime」を手掛けるロボット研究者だ。さぞ幼少期からロボットに強い関心を持ち、機械いじりに熱中していたのかと思いきや、そんなこともないようだ。
吉藤:私は昔からロボットが好きだったわけではありません。一番得意だったのは折り紙です。私には病気療養などの理由で3年半ほど不登校だった時期があります。学校に居場所がなく、天井ばかりを眺め続ける孤独で辛い日々でした。当時の唯一の趣味が折り紙で。朝から晩まで14時間ずっと折り続けたこともありました。その様子を心配した母親が「折り紙を折れるんだったら、ロボットを作れるに違いない」と考え、私が中学1年生のときにロボットコンテストに申し込んでくれたんです。言われるままに出場したところ、はじめてプログラミングを経験したのですが、運よく優勝することができました。

ノーベル賞受賞者の一言に背中を押される
ここから吉藤さんの運命は動き出す。ロボットコンテスト優勝後は工業高校へ進学。得意の折り紙を教えに特別支援学校へ赴いた際に見かけた電動車いすが使いづらそうだったことから、部活の仲間とともに車いすの開発に打ち込んだ。その結果、高校2年生のときに高校生・高専生を対象とした科学技術の自由研究コンテスト「JSEC」(Japan Science & Engineering Challenge)で文部科学大臣賞の受賞を果たしたのだった。吉藤:ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊教授が名誉アドバイザーを務められた「JSEC」に出場した私たちは、「傾かない車いす」を作りました。自動車で車道から歩道に移動する際、車体が傾きますよね。そこで傾かずに段差を上がれるよう、改造したタイヤ・ホイールを備えた車いすを発明したんです。この車いすを見た小柴先生に「君は研究者に向いているよ。もっと研究したらいい」と言っていただきました。その会場が日本科学未来館でした。私にとって、様々な教授にお会いし、後に早稲田大学に進学するきっかけを作ってくれた場所でもあります。

AI開発を「虚しい」と思った理由
「もう一つの身体があればいい」という思いは、早稲田大学在学中に開発した分身ロボット「OriHime」として形となる。だが、発明に至るまでには紆余曲折があったようだ。吉藤:私は高校時代、車椅子でも移動が難しい人が孤独を解消できるよう、人工知能の友達ロボットを作ろうと考えました。人と話すことが苦手だけど、気を遣いたくなくて、でも寂しいという人が行き着く先って、往々にして人工知能の友達を作ることだったりするのですが、私もその例に漏れなかったわけです。ところが、1年ほど開発に取り組んだところで「虚しい」と思うようになってしまいました。私がロボットコンテストへの出場をきっかけに不登校から復帰できたように、人生が変わる瞬間は「人との出会い」によって形作られていくものだと思います。しかし、移動困難な人はその機会を得ることができない人生を歩んでいる。後に出会った寝たきりの親友は「移動できない最大のハンディキャップは、人生に出会いと発見がないことなんだ」と言っていました。だとしたら、彼らが人生の中で出会いを得られる状況を作るアプローチをしていくべきだと考え、人工知能の開発をやめたんです。
人工知能開発を諦めた吉藤さんが次に着目したのはVRだ。現実世界からVR=仮想現実の世界へアクセスするには、ゴーグル型のディスプレイ「ヘッドマウントディスプレイ」を頭に装着する必要がある。仮想空間上では、性別や見た目を変えることができ、身体的なハンディキャップもなく自由に動き回ることが可能だ。吉藤さんは「寝たきりで身体を動かせない人たちにとって、オンライン世界はもはやリアル。そういった人がリアルへダイブするための『逆ヘッドディスプレイ』を作れないだろうか」と発想し、OriHimeを開発したという。
OriHimeをビジネスに昇華させた理由は?
吉藤さんの生涯のテーマは「孤独の解消」。この課題解決に向けてOriHimeをビジネスに昇華させた裏側には、ある人物からの助言があった。吉藤:早稲田大学在学中に参加したJSEC歴代優勝者が集まる交流会で、私の2大会後に優勝した結城さんという女性と出会いました。OriHimeを開発したばかりの私は進路に悩んでいたのですが、ロンドン大学でビジネスを学んだ経験のある彼女から「これビジネスにしなよ」と勧められたんです。当時の私はビジネスのビの字も知らず「あまり興味ないな」と答えました。すると結城さんは「バカ野郎」と。「吉藤が本当にやりたいことは『孤独の解消』のはず。であれば、孤独を解消された世界をちゃんとイメージしなければダメだよ」と怒られたんです。さらに、「身体が弱い吉藤がもしも早くに亡くなったとしたら、分身ロボットのメンテナンスをする人がいなくなり、サービス自体が終了してしまう。それではプロジェクトが自立していない」と指摘された上で、「単に分身ロボットを作りたいだけなのか、それとも、自分がいなくなった後も維持される社会の仕組みを作りたいのか」と問われたんです。私は「確かに」と納得しました。この分身ロボットのサービスを維持する方法として、結城さんはビジネス化を提案してくれたわけです。以降、結城さんと一緒にビジネスの勉強をし、計画書を書き、ビジネスコンテストに参加するなどして、少しずつビジネスとしての形を作っていきました。
こうして吉藤さんは2012年、結城さんらとともに株式会社オリィ研究所を設立。現在、同社の事業としてOriHimeが働く「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」を運営しており、お客さんからの反応は上々だという。その人気の理由とは?
吉藤:分身ロボットカフェで分身ロボットを遠隔操作する「パイロット」を務めてくださっている方は現在、全国に90名ほどいます。メニューを配膳し、オーダーを取ることはもちろん、コーヒーを作るバリスタロボットもいたりします。普通のカフェとの違いは、ロボットの店員さんがよくしゃべることです。普通のカフェだったら店員さんがずっと話しかけてきたらちょっと嫌じゃないですか。でも、ロボットカフェでは分身ロボットがずっとお客さんのそばにいて、30~40分ぐらいしゃべり続けていることが逆にウケているんです。パイロットのメンバーたちもOriHimeを介してであれば緊張せずに話せるみたいです。また、お客様もロボットの中の人に「どこに住んでいるんですか?」「前職は何をされていたんですか?」などと積極的にコミュニケーションを取られているようです。このように、分身ロボットにより自然とお互いが自己開示できる状態を作れることは一つ面白い発見でした。OriHimeは「心の車いす」でありながら、コミュニケーション能力を増幅してくれるツールとしても機能しているんです。


『ゲゲゲの鬼太郎』の「目玉おやじ」のような新サービスとは?
25年4月には9月30日までの期間限定店舗として、デンマークで分身ロボットカフェがオープンした。このようにOriHimeの活躍の場が広がる一方で、課題もあるという。吉藤:分身ロボットが街を走行することは技術的には可能です。ただ道交法が厳しく、現状では日本橋のお店からOriHimeは出ることができません。街を自由に移動できるようになれば、お客様をガイドすることや、ウィンドウショッピングを楽しむこともできるかもしれない。そんなふうに将来的には、街の中で車いすの方と同じように心の車いすが走れる状態を作りたいと考えています。ただ、今あえてロボットの姿で自走する必要はないとも思っていて。分身なのだから小さくてもいいわけですね。なので最近開発した小さいOriHimeを海外の方の肩に乗せて、通訳やガイドをするという新しいサービスを実験的に展開しています。家から出ることができないけど、英語と日本語を話せてガイドができるという方がパイロットを務めているのですが、これは「肩乗りOriHime」と呼んでいます。ちょうど『ゲゲゲの鬼太郎』に出てくる目玉おやじのイメージですね。
孤独の解消された社会を実現するべく、OriHimeの持つ可能性を拡張し続ける吉藤さん。最後に彼にとっての挑戦、そしてその先にあるFreude=喜びとは何かと尋ねると、こんな答えが返ってきた。
吉藤:私は身体が弱く、昔から様々な機会を逃してきました。この状態がさらに悪化し、いつか家から出られなくなるかもしれないとずっと恐れています。だからこそ、分身ロボットによりベッドから社会参加し続けられる未来を実現させたいと考え、活動しています。よく「障がい者雇用を行っているいい人」と言われがちなんですけど、私はいい人でもないし、いいことがやりたいわけでもありません。私は孤独を解消することで「寝たきりの先」を作りたいのです。そのために、寝たきりの先輩たちに協力してもらい、研究をしているわけです。なので、将来は自分の身体を自分で介護していきたい。誰かに付きっきりで横にいてもらうのではなく、もう一つの身体を使って水を飲んだり、寝返りをサポートさせたり、服を着替えたりと、身体が全く動かなくても、自分で自分のことができるようにしていきたいんです。その状態を10年以内には実現させたいと思っています。
(構成=小島浩平)
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。