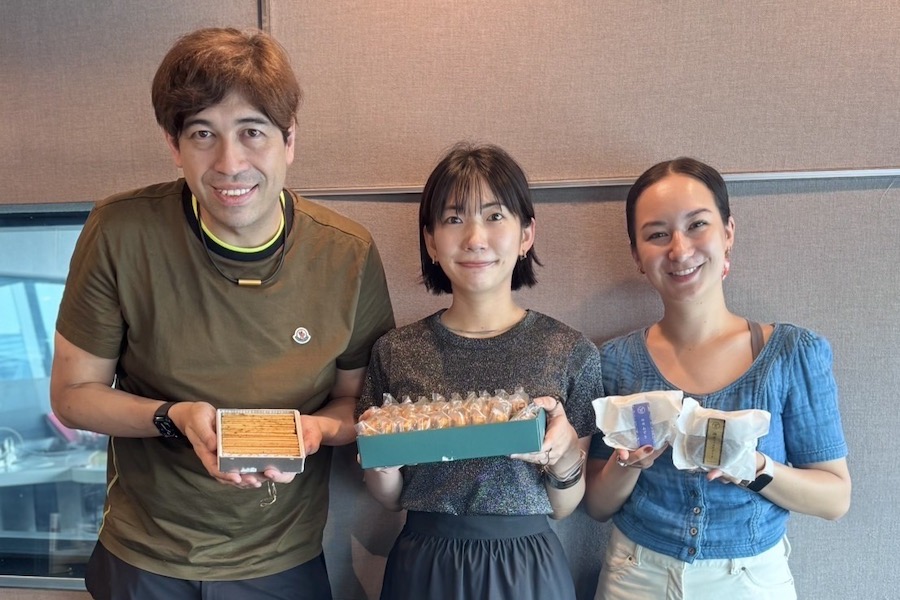映画プロデューサーの松井俊之さんが、最新作『この夏の星を見る』の制作・宣伝へのこだわりを語った。
松井さんが登場したのは、7月9日(水)放送のJ-WAVE『STEP ONE』(ナビゲーター:サッシャ、ノイハウス萌菜)のコーナー「SAISON CARD ON THE EDGE」だ。
サッシャ:映画のプロデューサーとは、何をやる人ですか?
松井:簡単に言うと、映画はたくさんの人が関わって、大きなお金が動くので、1個の事業を起業するみたいなイメージです。
サッシャ:社長ですか?
松井:そうですね。「全責任を持つ」という意味では、社長かもしれない。
サッシャ:業務の内容としては、具体的に何をするのですか?
松井:ものすごく多岐にわたるんですけど、まず企画書を作るという仕事があります。「どういう作品にしたいか」や「なぜいまなのか」「誰に届けたいのか」といったことをまとめます。
ノイハウス:ビジネスで言うと「どういう事業か」みたいなことですよね。
サッシャ:「採算が取れるのか」というところもあるわけですよね。
松井:「採算が取れるのか」に関しては、脚本という事業そのものの設計図を作って、それにいくらかかるのか、それをどうやって取り戻すのか、どうやってもうけを出すのかっていうところまでがビジネスなんですよね。そこまでひっくるめてプロデューサーの責任です。
サッシャ:監督や主演を決めたり、提案したりするのもプロデューサーですか?
松井:はい。「どういう作品にしたいか」というところで「どういう監督に撮らせたいか」や「どういう役者にやっていただきたいか」みたいなところ(を考えるまで)が、プロデューサーの範疇なんですよ。
ノイハウス:イメージ全般を決める、まとめるということですね。
松井:「負う責任」みたいなことは変わりませんが、作り方というのが違います。一概には言えないんですけど、アニメーションのほうが実写より長く時間がかかったり、たくさんの人が必要だったりするので、事業計画や設計図を立てていく段階で、多少スキームが違ってくることはありますね。
サッシャ:2022年公開の『THE FIRST SLAM DUNK』もプロデュースされて、大ヒットしました。『SLAM DUNK』そのものが、連載もアニメ放映もだいぶ前に終わっているなかで、めちゃくちゃヒットして「すごいな」と思ったのですが、これはなぜでしょう?
松井:ヒットの要因そのものは、分析するといろいろあると思います。ただ、本質的には、原作者の井上雄彦先生の、原作を連載されているときからのファンとの向き合い方。そこから先、長い年月かけて消費されていかないようにブランディングをされて、“ファンファースト”でお客さんと向き合って築いてきた時間や信頼という積み重ねがあったうえでの『THE FIRST SLAM DUNK』だったので、やっぱり井上雄彦先生のブランディングが本質だと思います。
サッシャ:描き方とか、すごく細かかったじゃないですか。大変だったでしょう?
松井:そうですね。アニメーションはやり直しがきくので、「追求し続けていくとキリがない」というところはアニメーションのよさでもあり、難しいところでもあるということですね。
サッシャ:私も観て、いろいろ考えさせられましたし、感動もしました。
ノイハウス:マスクの光景とかも、まだ数年前のことなのに「懐かしい」と思ってしまう自分がいたり、私は当時もう学生ではなかったので「こういうことを感じていたのか」という、あのときの(学生たちの)葛藤にも涙してしまいました。
松井:ありがとうございます。いま、公開してちょうど5~6日くらい経ちましたが(※オンエア時)、SNSを中心に観てくださった方の感想もいただいています。当時、全員が経験しているコロナ禍なので「いま思い返すと自分たちも大変だったけど、学生たちはこういう思いをしていたのかということを考えると、学生たちに観てほしいな」という声もありますが、ちょうど試験中で、まだ観に行けていないという学生が多くて……。
サッシャ:じゃあ、ロングランしないとダメですね!
松井:はい。これからぜひ、学生の方にも観ていただければと思います。
松井:2023年に、辻村先生がこの小説を新聞連載から始めて(書籍として)出されました。(コロナ禍に)嫌な思いや、つらい思いをされた方もいっぱいいたと思うので「そこをどういうタイミングで振り返るのか」というのはありましたが、「ついにこういう小説が出てきたか」と。映画にするのには最低でも2~3年かかるので、みんなが「そのときのことがあったから、いまがある」と思ったり、いまをより幸せに、有意義に生きるためになる映画になるといいなと思ったりして、企画をしました。
サッシャ:本当に大変な時期でしたが、同時に「星に出会う」ことも含め、こういうことがなければなかった出会いもあり、そういうこともすごく考えさせられますね。
松井:そうですね。リモートのありがたみなど、得たものもあると思うので、それを確認してもらえたらいいなと思います。
ノイハウス:今回、キャストやスタッフの方々を集めるにあたってのこだわりもあったと伺っています。
松井:いまの映画界は、次世代の若い方が出て勝負するというチャンスがあんまりないんですよね。ちょうどコロナ禍を描いた作品でもあるので、学生だったときにコロナを経験した人たちを含めて、次世代の方でオーディションをして、そのころの経験を語っていただいて、役を決めていきました。スタッフも若手で「みんなで思いをひとつにして、1個の作品を作り上げる」という意味でチャンスになればいいなという思いがありました。
サッシャ:だから、リアリティがあるんですね。
松井:そのころのことを、みんなに瞬時に思い出していただけるような仕掛けは作らないといけなかったので、リアリティはかなりこだわって作りました。
サッシャ:そういう意味では、マスク(をしての撮影)じゃないですか。大変だったでしょう?
松井:マスクで芝居をしていただくのは、いちばんハードルが高かったです。マスクをした状態で目の輝きとか表情とか、そういうところもひっくるめて、若い人たちなんだけど「そういう実力がある人たち」という感じで、キャスティングはしましたね。
【関連記事】マスク着用でも、俳優の目に星が宿っている─原作者・辻村深月が映画『この夏の星を見る』で感動したポイントは?
松井:映画って、洋画・邦画問わず、夜空や星空を表現するのがあまり得意じゃないメディアなんです。今回は、そこへの挑戦もあって、ナイトカメラマンっていう天体を撮るカメラマンさんに、各地に写真を撮りに行っていただきました。そして、画面のそちらの向きにある星にVFX(視覚効果)で本物の星を貼りつけて、さらに輝きもリアルにするために調整して、という感じで作りました。
サッシャ:『THE FIRST SLAM DUNK』ではプロモーションの仕方も独特でしたが、プロモーションという面では今回はどうでしたか?
松井:『THE FIRST SLAM DUNK』のときは井上雄彦先生に作り上げてきたブランディングがあったので、その本質を大事にするというのをすごく心がけたのですが、今回も同じクリエイティブディレクターの方やクリエイティブプロデューサーの方にご協力いただいて、「ブランディングを大事にする宣伝」を心がけました。SNSもメインビジュアルも、予告編も、一貫してブランディング統制を取って、世界観をひとつにしています。
サッシャ:SNSの縦型動画だったり、いろいろな打ち出し方がありますよね。
松井:SNSの縦型動画は制作のほうとリンクしています。群像劇で、たくさんキャラクターが出てくるのですが、映画は2時間なのでその人たちの深掘りができない。だから、それを補填して深みを出すために縦型動画で発信していて、それを観てから気持ちを入れて映画を観に行っていただいてもいいですし、映画を観ていただいてからそっちを観てもっと深掘ってもいいという仕掛けにしています。
サッシャ:(J-WAVEとコラボレーションでお届けしている)『ハラカド天文部』のPodcastもそういう意図で?
松井:『ハラカド天文部』は、バックヤードって言うんですかね、(先ほど話した)天体を撮るカメラマンとか「天体はこういうふうに見えるんだよ」と監修する先生とか、今回、岡部たかしさんが演じた綿引先生という役にはモデルの先生がいらっしゃって、その先生にも出ていただきました。こちらもクリエイター側を深掘りして、世界観全部を楽しんでいただけるように、宣伝の一貫としてやっています。
最後にサッシャは「プロデュースする作品を通し、どんなことを伝えたいか」と、松井さんの思いを訊いた。
松井:映画は「なくてはいけないものか論」というのがあるのですが、食べるとか眠るとか、なくてはいけない事業っていろいろあると思います。エンタメも人の心を豊かにしたり、幸せにしたりできるジャンルだと思うので、そういう思いになっていただけるような作品を作っていきたいと思っています。
サッシャ:「あるべきものなんだ」と。
松井:に、なりたいですね。「これがあってよかった、ありがとう」と言ってもらえるような作品を志しています。
映画『この夏の星を見る』の詳細は公式サイトまで。
J-WAVE『STEP ONE』のコーナー「SAISON CARD ON THE EDGE」では、ニューノーマル時代のエッジにフォーカス。放送は月曜~木曜の10時10分ごろから。
松井さんが登場したのは、7月9日(水)放送のJ-WAVE『STEP ONE』(ナビゲーター:サッシャ、ノイハウス萌菜)のコーナー「SAISON CARD ON THE EDGE」だ。
起業に近い? 映画プロデューサーのお仕事
松井俊之さんは、映画会社、テレビ局、フリーランスを経て、東映アニメーションで『THE FIRST SLAM DUNK』をプロデュース。現在は株式会社FLARE CREATORSの取締役/エグゼクティブプロデューサーとして活躍中だ。これまでプロデューサーを務めた作品は、『ロックンロールミシン』や『BALLAD 名もなき恋のうた』などの実写から『Re:キューティーハニー』『ポッピンQ』などのアニメまで幅広く手がけている。2022年公開の『THE FIRST SLAM DUNK』では第46回日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作品賞、第42回藤本賞を受賞した。サッシャ:映画のプロデューサーとは、何をやる人ですか?
松井:簡単に言うと、映画はたくさんの人が関わって、大きなお金が動くので、1個の事業を起業するみたいなイメージです。
サッシャ:社長ですか?
松井:そうですね。「全責任を持つ」という意味では、社長かもしれない。
サッシャ:業務の内容としては、具体的に何をするのですか?
松井:ものすごく多岐にわたるんですけど、まず企画書を作るという仕事があります。「どういう作品にしたいか」や「なぜいまなのか」「誰に届けたいのか」といったことをまとめます。
ノイハウス:ビジネスで言うと「どういう事業か」みたいなことですよね。
サッシャ:「採算が取れるのか」というところもあるわけですよね。
松井:「採算が取れるのか」に関しては、脚本という事業そのものの設計図を作って、それにいくらかかるのか、それをどうやって取り戻すのか、どうやってもうけを出すのかっていうところまでがビジネスなんですよね。そこまでひっくるめてプロデューサーの責任です。
サッシャ:監督や主演を決めたり、提案したりするのもプロデューサーですか?
松井:はい。「どういう作品にしたいか」というところで「どういう監督に撮らせたいか」や「どういう役者にやっていただきたいか」みたいなところ(を考えるまで)が、プロデューサーの範疇なんですよ。
ノイハウス:イメージ全般を決める、まとめるということですね。
『THE FIRST SLAM DUNK』ヒットの理由を考察
実写、アニメーションと、幅広いジャンルの映画制作に携わってきた松井さん。ノイハウスは「実写とアニメーションの、プロデューサーの役割としての違い」について訊いた。松井:「負う責任」みたいなことは変わりませんが、作り方というのが違います。一概には言えないんですけど、アニメーションのほうが実写より長く時間がかかったり、たくさんの人が必要だったりするので、事業計画や設計図を立てていく段階で、多少スキームが違ってくることはありますね。
サッシャ:2022年公開の『THE FIRST SLAM DUNK』もプロデュースされて、大ヒットしました。『SLAM DUNK』そのものが、連載もアニメ放映もだいぶ前に終わっているなかで、めちゃくちゃヒットして「すごいな」と思ったのですが、これはなぜでしょう?
松井:ヒットの要因そのものは、分析するといろいろあると思います。ただ、本質的には、原作者の井上雄彦先生の、原作を連載されているときからのファンとの向き合い方。そこから先、長い年月かけて消費されていかないようにブランディングをされて、“ファンファースト”でお客さんと向き合って築いてきた時間や信頼という積み重ねがあったうえでの『THE FIRST SLAM DUNK』だったので、やっぱり井上雄彦先生のブランディングが本質だと思います。
サッシャ:描き方とか、すごく細かかったじゃないですか。大変だったでしょう?
松井:そうですね。アニメーションはやり直しがきくので、「追求し続けていくとキリがない」というところはアニメーションのよさでもあり、難しいところでもあるということですね。
コロナ禍の学生たちを描いた最新作が公開中
そんな松井さんが総合プロデューサーを務めた最新作『この夏の星を見る』が、7月4日(金)に全国公開された。直木賞作家・辻村深月の小説を原作とした本作は、2020年のコロナ禍の物語だ。さまざまな制限がある学校生活のなかで、茨城と東京、長崎に住む学生たちが、オンラインで「スターキャッチコンテスト」を開催する様子が描かれている。映画「この夏の星を見る」| 本予告 2025年7月4日(金)公開
ノイハウス:マスクの光景とかも、まだ数年前のことなのに「懐かしい」と思ってしまう自分がいたり、私は当時もう学生ではなかったので「こういうことを感じていたのか」という、あのときの(学生たちの)葛藤にも涙してしまいました。
松井:ありがとうございます。いま、公開してちょうど5~6日くらい経ちましたが(※オンエア時)、SNSを中心に観てくださった方の感想もいただいています。当時、全員が経験しているコロナ禍なので「いま思い返すと自分たちも大変だったけど、学生たちはこういう思いをしていたのかということを考えると、学生たちに観てほしいな」という声もありますが、ちょうど試験中で、まだ観に行けていないという学生が多くて……。
サッシャ:じゃあ、ロングランしないとダメですね!
松井:はい。これからぜひ、学生の方にも観ていただければと思います。
当時、学生だった“次世代”の俳優をキャスティング
2023年より『この夏の星を見る』の企画をスタートしたという松井さん。当時の思いを、次のように語る。松井:2023年に、辻村先生がこの小説を新聞連載から始めて(書籍として)出されました。(コロナ禍に)嫌な思いや、つらい思いをされた方もいっぱいいたと思うので「そこをどういうタイミングで振り返るのか」というのはありましたが、「ついにこういう小説が出てきたか」と。映画にするのには最低でも2~3年かかるので、みんなが「そのときのことがあったから、いまがある」と思ったり、いまをより幸せに、有意義に生きるためになる映画になるといいなと思ったりして、企画をしました。
サッシャ:本当に大変な時期でしたが、同時に「星に出会う」ことも含め、こういうことがなければなかった出会いもあり、そういうこともすごく考えさせられますね。
松井:そうですね。リモートのありがたみなど、得たものもあると思うので、それを確認してもらえたらいいなと思います。
ノイハウス:今回、キャストやスタッフの方々を集めるにあたってのこだわりもあったと伺っています。
松井:いまの映画界は、次世代の若い方が出て勝負するというチャンスがあんまりないんですよね。ちょうどコロナ禍を描いた作品でもあるので、学生だったときにコロナを経験した人たちを含めて、次世代の方でオーディションをして、そのころの経験を語っていただいて、役を決めていきました。スタッフも若手で「みんなで思いをひとつにして、1個の作品を作り上げる」という意味でチャンスになればいいなという思いがありました。
サッシャ:だから、リアリティがあるんですね。
松井:そのころのことを、みんなに瞬時に思い出していただけるような仕掛けは作らないといけなかったので、リアリティはかなりこだわって作りました。
サッシャ:そういう意味では、マスク(をしての撮影)じゃないですか。大変だったでしょう?
松井:マスクで芝居をしていただくのは、いちばんハードルが高かったです。マスクをした状態で目の輝きとか表情とか、そういうところもひっくるめて、若い人たちなんだけど「そういう実力がある人たち」という感じで、キャスティングはしましたね。
【関連記事】マスク着用でも、俳優の目に星が宿っている─原作者・辻村深月が映画『この夏の星を見る』で感動したポイントは?
夜空、プロモーション… 細部にわたるこだわり
さまざまなこだわりを持って制作にあたった『この夏の星を見る』は、星空のシーンも印象的だ。「まるで本物を見ているかのようだった」とノイハウスも絶賛する星空は、どのようにして撮影されたのだろうか。松井:映画って、洋画・邦画問わず、夜空や星空を表現するのがあまり得意じゃないメディアなんです。今回は、そこへの挑戦もあって、ナイトカメラマンっていう天体を撮るカメラマンさんに、各地に写真を撮りに行っていただきました。そして、画面のそちらの向きにある星にVFX(視覚効果)で本物の星を貼りつけて、さらに輝きもリアルにするために調整して、という感じで作りました。
サッシャ:『THE FIRST SLAM DUNK』ではプロモーションの仕方も独特でしたが、プロモーションという面では今回はどうでしたか?
松井:『THE FIRST SLAM DUNK』のときは井上雄彦先生に作り上げてきたブランディングがあったので、その本質を大事にするというのをすごく心がけたのですが、今回も同じクリエイティブディレクターの方やクリエイティブプロデューサーの方にご協力いただいて、「ブランディングを大事にする宣伝」を心がけました。SNSもメインビジュアルも、予告編も、一貫してブランディング統制を取って、世界観をひとつにしています。
サッシャ:SNSの縦型動画だったり、いろいろな打ち出し方がありますよね。
松井:SNSの縦型動画は制作のほうとリンクしています。群像劇で、たくさんキャラクターが出てくるのですが、映画は2時間なのでその人たちの深掘りができない。だから、それを補填して深みを出すために縦型動画で発信していて、それを観てから気持ちを入れて映画を観に行っていただいてもいいですし、映画を観ていただいてからそっちを観てもっと深掘ってもいいという仕掛けにしています。
サッシャ:(J-WAVEとコラボレーションでお届けしている)『ハラカド天文部』のPodcastもそういう意図で?
松井:『ハラカド天文部』は、バックヤードって言うんですかね、(先ほど話した)天体を撮るカメラマンとか「天体はこういうふうに見えるんだよ」と監修する先生とか、今回、岡部たかしさんが演じた綿引先生という役にはモデルの先生がいらっしゃって、その先生にも出ていただきました。こちらもクリエイター側を深掘りして、世界観全部を楽しんでいただけるように、宣伝の一貫としてやっています。
最後にサッシャは「プロデュースする作品を通し、どんなことを伝えたいか」と、松井さんの思いを訊いた。
松井:映画は「なくてはいけないものか論」というのがあるのですが、食べるとか眠るとか、なくてはいけない事業っていろいろあると思います。エンタメも人の心を豊かにしたり、幸せにしたりできるジャンルだと思うので、そういう思いになっていただけるような作品を作っていきたいと思っています。
サッシャ:「あるべきものなんだ」と。
松井:に、なりたいですね。「これがあってよかった、ありがとう」と言ってもらえるような作品を志しています。
映画『この夏の星を見る』の詳細は公式サイトまで。
J-WAVE『STEP ONE』のコーナー「SAISON CARD ON THE EDGE」では、ニューノーマル時代のエッジにフォーカス。放送は月曜~木曜の10時10分ごろから。
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。
radikoで聴く
2025年7月16日28時59分まで
PC・スマホアプリ「radiko.jpプレミアム」(有料)なら、日本全国どこにいてもJ-WAVEが楽しめます。番組放送後1週間は「radiko.jpタイムフリー」機能で聴き直せます。
番組情報
- STEP ONE
-
月・火・水・木曜9:00-13:00
-
サッシャ、ノイハウス萌菜