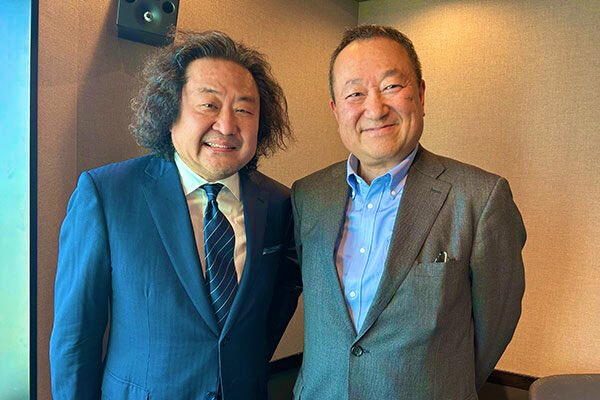タレントで歌手のミッツ・マングローブが、学生時代に過ごしたロンドンの思い出や、ドイツでの忘れられないエピソードを語った。
ミッツが登場したのは、ゲストに様々な国での旅の思い出を聞く、J-WAVEで放送中の番組『ANA WORLD AIR CURRENT』(ナビゲーター:葉加瀬太郎)。オンエアは6月22日(土)。
ミッツは小学5年生の終わり、父親の転勤により家族でロンドンに移り住んだという。
ミッツ:いわゆる企業の駐在員ですね。そこから中学卒業まで4年間ずっと日本人学校に通っていました。家族で住んでいるときはパットニーでしたね。
葉加瀬:パットニーは日本人が多いよね。
ミッツ:細かい話をすると、私が転入する前の年まで日本人学校はカムデンにあったんですよ。なので、当時日本人は北にかたまっていました。そんな中、日本人学校が中西部に移転するので、ロンドンのテムズ川より南側にも日本人が住み出すことになりました。私が住んでいたパットニー、テニスで有名なウィンブルドン、大きな公園があるリッチモンドなどに日本人が移り住んできたわけです。ちょうどそういう時代でした。
登校の際は、パットニーからスクールバスに乗り、バーンズ・コモンを抜け、ハマースミス橋を渡って高速に乗って学校に向かっていたという。
葉加瀬:小学5年生から中学卒業までって、わりと多感な時期じゃないですか。ミッツが覚えている当時のロンドンの雰囲気はどんな感じでした?
ミッツ:サッチャー政権の末期だったので、もっとも景気が悪かったんじゃないですかね。天気というよりも、街自体がどんよりしていて、「こういうところに来ちゃったんだな」と思っていました。一方、当時の日本はバブルの時代ですから、物価的なことも含めて日本人としてはすごく暮らしやすかったとは思うんですよ。ただね、通信とかも含めてまだ不便な時代ですから、私はとにかく日本の情報を渇望していました。
葉加瀬:そうですよね。
ミッツ:テレビもないしネットもないし、くるのは朝日新聞の衛星版だけ。新聞のテレビのラテ欄を見て、「こんな人たちが流行っているんだな」「この人たちが別れたんだ」とかを知りました。それを学校でみんなと情報交換して、どうにか日本の情報についていっていましたね。
葉加瀬:逆にロンドンの音楽のヒットチャートは?
ミッツ:それはそれでハマりましたよ。一日中チャートミュージックを流しているラジオがどこに行ったって流れていますし、スクールバスでもかかっていました。ちょうど私が行った頃はユーロビートが大ブームでしたから、カイリー・ミノーグやペット・ショップ・ボーイズが入れ代わり立ち代わり毎週1位だった時代でしたね。ああいうサウンドはすごく原点になっています。
葉加瀬:音楽的にはイケイケだよね(笑)。
ミッツ:日本だけがバブルで4つ打ちが流行っていたかというと、そうでもなくて。世界的にキラキラしたものが輝いていた時代でしたね。
ミッツ:1987年というとイワン・レンドルやボリス・ベッカー、女子はマルチナ・ナブラチロワがまだ勝っていたのかな? でも、ドイツのシュテフィ・グラフが出てきて女王が交代する時代でした。(ウィンブルドン)のセンターコートはさすがに事前予約をして抽選を受けないと見られないんですけど、第1コートまでは出入り自由なんですよ。なので、私たちが学校に行っているあいだ、母親がチケットを買って試合を見るんです。自分たちが学校を終えるとウィンブルドンのゲートの前で母親と待ち合わせをして、その券をもらって夕方の試合を見ていました。
葉加瀬:なるほどね。
ミッツ:それこそ、伊達公子さんがデビューした1989年の試合も見ていますし、あれは贅沢でしたね。あの時間、あの季節って22時ぐらいまで明るいじゃないですか。試合もサドンデスで21時過ぎぐらいまでやっていますし、電車で2駅ぐらいだったので、終わったらパッと帰っていました。
葉加瀬:いい季節にウィンブルドンがあるよね。みんなで飲み物を飲んでイチゴを食べて。
ミッツ:イチゴを食べる文化ってまだあるんですか?
葉加瀬:ずっとやっているよ(笑)。
ミッツ:ウィンブルドンってイチゴのイメージが強すぎて、イチゴって6月の果物だと思っていたんですよ。日本って3月ぐらいにイチゴフェアをやりますよね。
葉加瀬:ピクニックの感覚でウィンブルドンを見に行くところがあるよね。
ミッツ:今はライブビューイングもすごいですよね。
葉加瀬:ミッツもテニスはわりと真剣にやっていた?
ミッツ:いやいや(笑)。でもスポーツで唯一やったのは水泳とテニスぐらいかな。ただ、脳内妄想テニスは散々やったので、日本人女子プロテニスプレイヤーとして、私はウィンブルドンで3回勝っているんですよ。
葉加瀬:妄想でね(笑)。
ミッツ:いわゆるクラシック以外の、ポップス、ロック、ジャズ、ヒップホップなどの実技とビジネス、法律、パフォーマンス、スタジオワーク全般を教えてくれるコースを見つけて、そこに行きたいと思いました。
葉加瀬:歌や楽器を演奏するような実演よりは、もっとロジカルなものですか?
ミッツ:入試はエッセイとオーディションで、自分が作った曲をピアノで弾き語りしましたね。それで受かって2年ちょっと行って、3年生は卒論と卒業制作だけなんですよ。向こうでもデモテープを作っていろいろスタジオやレーベルに持って行ったりしたんですけど、もちろん無理で。それで一度日本で頑張ろうって感じで3年生の途中で帰ってきちゃいました。
葉加瀬:なるほど。ウエストミンスターに通っていたときに、ソーホーにけっこう通っていたそうですね?
ミッツ:はい。親元を離れて自由の身なわけじゃないですか。ある程度、自我も対外的にも相互理解が得られているので、「自分はこういう人です」とカミングアウトしているわけです。まあ毎晩ソーホーで飲んでいましたね。で、クラブに行って男を引っかけ、引っかけられ、私の唯一のモテ期です。1999年の夏。リッキー・マーティンが流行っていました。
葉加瀬:時代がわかるなあ。
ミッツ:ノースリーブのTシャツを着ていくんですよ。タバコを吸おうと思ってタバコを持つと、即座に4人ぐらいが火を点けてくれるっていう……(笑)。
葉加瀬:話を聞いていると、ロンドンはミッツの人生観のベースになっている感じがあるね。
ミッツ:めちゃくちゃありますね。思春期の頃の音楽や、20代前半のいわゆる性の解放もロンドンでしたから。その2本の柱で今も生きているって感じです。
ミッツ:ロンドンのソーホーのゲイクラブで、めちゃくちゃ美しい金髪の美少年と出会ったんですよ。
葉加瀬:ほう。
ミッツ:その子は旅行でロンドンに、夏休みで来ていたんです。どこから来ていたかというと、ドイツのミュンヘンです。私、その子を追っかけてミュンヘンに行ったんですよ(笑)。
葉加瀬:年齢は同じぐらいだったの?
ミッツ:私が23歳、相手が18、19歳ぐらいだった気がする。
葉加瀬:かわいかった?
ミッツ:もう、天使のような。名前とミュンヘンから来たっていう情報しか知らなかったんですけど、その子には年上のパパがいたんですよ。そのパパに見つかってしまい、引き離された、と私は思っているんです。だから悲劇的な別れをしたので、「ミュンヘンに行って彼を探し出してあのオヤジから救い出さなきゃいけない」と。
葉加瀬:まるで映画じゃん!
ミッツ:「1週間で帰ってきなさい」と周りの大人たちに言われていたので、区切りを設けてとりあえずミュンヘンに行きました。ミュンヘンって小さい街なんですけど100万人都市なわけです。だけど、ゲイタウンとなると限られてくるので、そこのエリアのあらゆる店に毎晩行きました。ミュンヘン中の若いゲイの子に「こういう子を知りませんか?」と似顔絵を見せて。でも「なんだこのおかしい日本人は」みたいな反応ですよ(笑)。
葉加瀬:それからどうしたの?
ミッツ:結局、会えませんでした。会えるわけがないんですけどね。だけど、その1週間でしこたま出会いはありましたね(笑)。
葉加瀬:行ってよかったね。
ミッツ:ミュンヘンの彼の特徴が襟足だったんですよ。本当にきれいな金髪で、襟足がちょっと長かったんです。東ヨーロッパの感じの襟足ってわかります?
葉加瀬:わかります。
ミッツ:ロンドンではあまりいない襟足でした。この襟足だったら後ろ姿でも見つけられると思ったんですけど、ミュンヘンに着いたら全員その襟足だったんですよ。「しまった!」って思いました(笑)。
葉加瀬:あはは(笑)。でもさ、会えなくてもよかったんだよ。そのときにバッと行動できる気持ちが大切だよね。
ミッツ:あの1週間の執念は忘れられない。映画にしたら楽しそうですよね。
葉加瀬:本当だよね。すごく素敵な話だよな。
葉加瀬太郎がお届けする『ANA WORLD AIR CURRENT』は、J-WAVEで毎週土曜19:00-20:00オンエア。
ミッツが登場したのは、ゲストに様々な国での旅の思い出を聞く、J-WAVEで放送中の番組『ANA WORLD AIR CURRENT』(ナビゲーター:葉加瀬太郎)。オンエアは6月22日(土)。
多感な時期をロンドンで過ごす
ミッツ・マングローブは10代から20代にかけておよそ7年間をロンドンで過ごし、1998年に慶應義塾大学法学部を卒業。2000年にドラァグクイーンとしてデビュー以来、さまざまな芸能活動を展開。女装歌手3人による音楽グループ「星屑スキャット」としても精力的に活動中だ。ミッツは小学5年生の終わり、父親の転勤により家族でロンドンに移り住んだという。
ミッツ:いわゆる企業の駐在員ですね。そこから中学卒業まで4年間ずっと日本人学校に通っていました。家族で住んでいるときはパットニーでしたね。
葉加瀬:パットニーは日本人が多いよね。
ミッツ:細かい話をすると、私が転入する前の年まで日本人学校はカムデンにあったんですよ。なので、当時日本人は北にかたまっていました。そんな中、日本人学校が中西部に移転するので、ロンドンのテムズ川より南側にも日本人が住み出すことになりました。私が住んでいたパットニー、テニスで有名なウィンブルドン、大きな公園があるリッチモンドなどに日本人が移り住んできたわけです。ちょうどそういう時代でした。
登校の際は、パットニーからスクールバスに乗り、バーンズ・コモンを抜け、ハマースミス橋を渡って高速に乗って学校に向かっていたという。
葉加瀬:小学5年生から中学卒業までって、わりと多感な時期じゃないですか。ミッツが覚えている当時のロンドンの雰囲気はどんな感じでした?
ミッツ:サッチャー政権の末期だったので、もっとも景気が悪かったんじゃないですかね。天気というよりも、街自体がどんよりしていて、「こういうところに来ちゃったんだな」と思っていました。一方、当時の日本はバブルの時代ですから、物価的なことも含めて日本人としてはすごく暮らしやすかったとは思うんですよ。ただね、通信とかも含めてまだ不便な時代ですから、私はとにかく日本の情報を渇望していました。
葉加瀬:そうですよね。
ミッツ:テレビもないしネットもないし、くるのは朝日新聞の衛星版だけ。新聞のテレビのラテ欄を見て、「こんな人たちが流行っているんだな」「この人たちが別れたんだ」とかを知りました。それを学校でみんなと情報交換して、どうにか日本の情報についていっていましたね。
葉加瀬:逆にロンドンの音楽のヒットチャートは?
ミッツ:それはそれでハマりましたよ。一日中チャートミュージックを流しているラジオがどこに行ったって流れていますし、スクールバスでもかかっていました。ちょうど私が行った頃はユーロビートが大ブームでしたから、カイリー・ミノーグやペット・ショップ・ボーイズが入れ代わり立ち代わり毎週1位だった時代でしたね。ああいうサウンドはすごく原点になっています。
葉加瀬:音楽的にはイケイケだよね(笑)。
ミッツ:日本だけがバブルで4つ打ちが流行っていたかというと、そうでもなくて。世界的にキラキラしたものが輝いていた時代でしたね。
ウィンブルドンといえばイチゴのイメージ?
スポーツが盛んなイギリスで学生時代を過ごしたミッツは、ウィンブルドンでのテニス観戦にハマっていたという。ミッツ:1987年というとイワン・レンドルやボリス・ベッカー、女子はマルチナ・ナブラチロワがまだ勝っていたのかな? でも、ドイツのシュテフィ・グラフが出てきて女王が交代する時代でした。(ウィンブルドン)のセンターコートはさすがに事前予約をして抽選を受けないと見られないんですけど、第1コートまでは出入り自由なんですよ。なので、私たちが学校に行っているあいだ、母親がチケットを買って試合を見るんです。自分たちが学校を終えるとウィンブルドンのゲートの前で母親と待ち合わせをして、その券をもらって夕方の試合を見ていました。
葉加瀬:なるほどね。
ミッツ:それこそ、伊達公子さんがデビューした1989年の試合も見ていますし、あれは贅沢でしたね。あの時間、あの季節って22時ぐらいまで明るいじゃないですか。試合もサドンデスで21時過ぎぐらいまでやっていますし、電車で2駅ぐらいだったので、終わったらパッと帰っていました。
葉加瀬:いい季節にウィンブルドンがあるよね。みんなで飲み物を飲んでイチゴを食べて。
ミッツ:イチゴを食べる文化ってまだあるんですか?
葉加瀬:ずっとやっているよ(笑)。
ミッツ:ウィンブルドンってイチゴのイメージが強すぎて、イチゴって6月の果物だと思っていたんですよ。日本って3月ぐらいにイチゴフェアをやりますよね。
葉加瀬:ピクニックの感覚でウィンブルドンを見に行くところがあるよね。
ミッツ:今はライブビューイングもすごいですよね。
葉加瀬:ミッツもテニスはわりと真剣にやっていた?
ミッツ:いやいや(笑)。でもスポーツで唯一やったのは水泳とテニスぐらいかな。ただ、脳内妄想テニスは散々やったので、日本人女子プロテニスプレイヤーとして、私はウィンブルドンで3回勝っているんですよ。
葉加瀬:妄想でね(笑)。
ソーホーで人生初の“モテ期”を満喫
ミッツは慶應大学を卒業後、イギリスのウエストミンスター大学で商業音楽全般を学んだ経歴を持つ。ミッツ:いわゆるクラシック以外の、ポップス、ロック、ジャズ、ヒップホップなどの実技とビジネス、法律、パフォーマンス、スタジオワーク全般を教えてくれるコースを見つけて、そこに行きたいと思いました。
葉加瀬:歌や楽器を演奏するような実演よりは、もっとロジカルなものですか?
ミッツ:入試はエッセイとオーディションで、自分が作った曲をピアノで弾き語りしましたね。それで受かって2年ちょっと行って、3年生は卒論と卒業制作だけなんですよ。向こうでもデモテープを作っていろいろスタジオやレーベルに持って行ったりしたんですけど、もちろん無理で。それで一度日本で頑張ろうって感じで3年生の途中で帰ってきちゃいました。
葉加瀬:なるほど。ウエストミンスターに通っていたときに、ソーホーにけっこう通っていたそうですね?
ミッツ:はい。親元を離れて自由の身なわけじゃないですか。ある程度、自我も対外的にも相互理解が得られているので、「自分はこういう人です」とカミングアウトしているわけです。まあ毎晩ソーホーで飲んでいましたね。で、クラブに行って男を引っかけ、引っかけられ、私の唯一のモテ期です。1999年の夏。リッキー・マーティンが流行っていました。
葉加瀬:時代がわかるなあ。
ミッツ:ノースリーブのTシャツを着ていくんですよ。タバコを吸おうと思ってタバコを持つと、即座に4人ぐらいが火を点けてくれるっていう……(笑)。
葉加瀬:話を聞いていると、ロンドンはミッツの人生観のベースになっている感じがあるね。
ミッツ:めちゃくちゃありますね。思春期の頃の音楽や、20代前半のいわゆる性の解放もロンドンでしたから。その2本の柱で今も生きているって感じです。
ドイツで経験した“執念の1週間”を振り返る
ミッツは忘れられない思い出として、1999年の夏にソーホーのゲイクラブで出会った美少年とのエピソードを語った。ミッツ:ロンドンのソーホーのゲイクラブで、めちゃくちゃ美しい金髪の美少年と出会ったんですよ。
葉加瀬:ほう。
ミッツ:その子は旅行でロンドンに、夏休みで来ていたんです。どこから来ていたかというと、ドイツのミュンヘンです。私、その子を追っかけてミュンヘンに行ったんですよ(笑)。
葉加瀬:年齢は同じぐらいだったの?
ミッツ:私が23歳、相手が18、19歳ぐらいだった気がする。
葉加瀬:かわいかった?
ミッツ:もう、天使のような。名前とミュンヘンから来たっていう情報しか知らなかったんですけど、その子には年上のパパがいたんですよ。そのパパに見つかってしまい、引き離された、と私は思っているんです。だから悲劇的な別れをしたので、「ミュンヘンに行って彼を探し出してあのオヤジから救い出さなきゃいけない」と。
葉加瀬:まるで映画じゃん!
ミッツ:「1週間で帰ってきなさい」と周りの大人たちに言われていたので、区切りを設けてとりあえずミュンヘンに行きました。ミュンヘンって小さい街なんですけど100万人都市なわけです。だけど、ゲイタウンとなると限られてくるので、そこのエリアのあらゆる店に毎晩行きました。ミュンヘン中の若いゲイの子に「こういう子を知りませんか?」と似顔絵を見せて。でも「なんだこのおかしい日本人は」みたいな反応ですよ(笑)。
葉加瀬:それからどうしたの?
ミッツ:結局、会えませんでした。会えるわけがないんですけどね。だけど、その1週間でしこたま出会いはありましたね(笑)。
葉加瀬:行ってよかったね。
ミッツ:ミュンヘンの彼の特徴が襟足だったんですよ。本当にきれいな金髪で、襟足がちょっと長かったんです。東ヨーロッパの感じの襟足ってわかります?
葉加瀬:わかります。
ミッツ:ロンドンではあまりいない襟足でした。この襟足だったら後ろ姿でも見つけられると思ったんですけど、ミュンヘンに着いたら全員その襟足だったんですよ。「しまった!」って思いました(笑)。
葉加瀬:あはは(笑)。でもさ、会えなくてもよかったんだよ。そのときにバッと行動できる気持ちが大切だよね。
ミッツ:あの1週間の執念は忘れられない。映画にしたら楽しそうですよね。
葉加瀬:本当だよね。すごく素敵な話だよな。
葉加瀬太郎がお届けする『ANA WORLD AIR CURRENT』は、J-WAVEで毎週土曜19:00-20:00オンエア。
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。
番組情報
- ANA WORLD AIR CURRENT
-
毎週土曜19:00-19:54
-
葉加瀬太郎