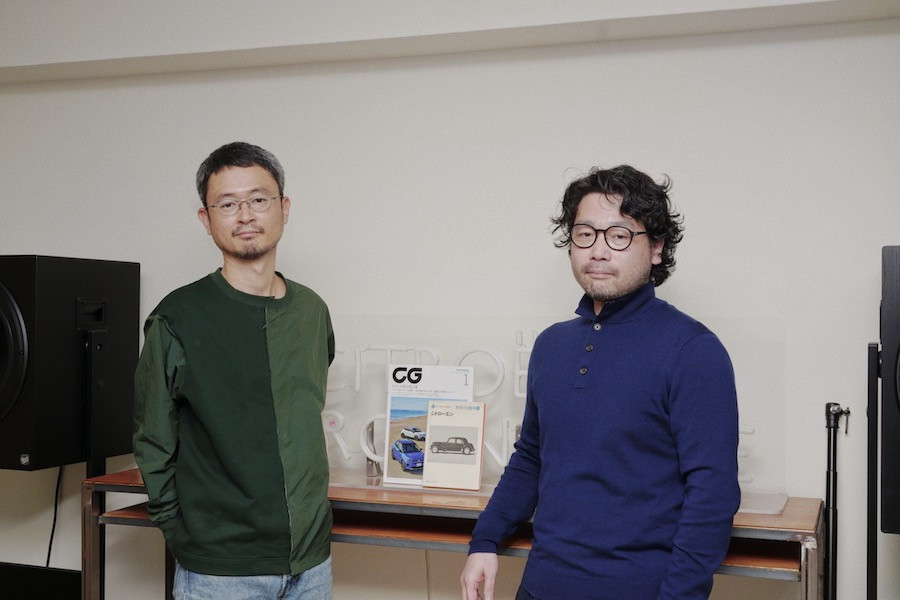
自動車雑誌『カーグラフィック』編集長の小野光陽さんが、これまでのキャリアを振り返り、シトロエンならではの魅力について語った。
小野さんが登場したのは、2025年12月20日(土)放送のJ-WAVE『CITROËN FOURGONNETTE』(ナビゲーター:長岡亮介)。ペトロールズの長岡が、心地よい音楽とともに、気の置けない仲間や時にはひとり語りで大人のライフスタイルを提案していく。
12月1日に発売された『カーグラフィック 2026年1月号』では、「フランス車の花と華」と題した特集を掲載。長岡は愛車である「シトロエン・AMI 6」とともに登場している。
長岡:このあいだ、特集の取材をしていただきまして、そのときに小野さんとご一緒しました。その節はありがとうございました。気持ちのいい天気の日でしたね。
小野:秋晴れでしたね。
長岡:『カーグラフィック』は日本の雑誌のなかでもかなりの歴史がありますよね。
小野:歴史のある雑誌で言うと、たとえば『モーターマガジン』さんがあるんですけども、2025年で70周年なんですね。『モーターマガジン』で働いていた高島鎮雄さんと、外部で協力されていた小林彰太郎が移籍されて作ったのが『カーグラフィック』です。
長岡:なるほど! 小野さんは編集長になってどれぐらいですか?
小野:2年目ですね。
長岡:雑誌の仕事をされるのは『カーグラフィック』が初めてですか?
小野:自動車だとそうですね。最初にミニカーやデザイン家電といったモノ系の雑誌をやっていました。
長岡:そうなんですか。車は昔からお好きとのことですが、『カーグラフィック』で実際にお仕事されてみてどうですか?
小野:責任感というか、看板が大きいので、それに恥じないものを作ろうという意識が勝ちますね。
長岡:『カーグラフィック』の真髄ってどこにあると感じますか?
小野:やっぱり実地、自分たちで取材することですね。特に昨今はそこを大事にしたいなと思っていて、海外も国内もできるだけ実際に触れて、人に会って取材をしたいです。
長岡:最初から順を追って聞きますね。まずイタリアには何をしに行ったのですか?
小野:パドバは語学留学で、モデナで自動車系のエンジニアリングの専門学校に通っていました。
長岡:すごい! なぜイタリアだったんですか?
小野:「イタリア車を作りたかった」という単純な理由です(笑)。
長岡:イタリアの車メーカーに入って設計をしたいという夢があったのですね。そのあとに帰国して、有名なノバ・エンジニアリングに入社された。F2の印象がありますが。
小野:F2やF3をやっていた時代もありましたが、(私が在籍していた頃は)スーパーGTを走らせたりしていました。あとは、直属の上司がF1解説でお馴染みの森脇基恭さんでした。
長岡:そうなんだ! ノバ・エンジニアリングでは何をされていたんですか?
小野:CAD/CAMですね。
長岡:図面を引いた車がレースを走っていたんですか?
小野:あとは、量産前のプロトタイプになったりしていました。
長岡:そして、国土交通省。こちらはどういった経緯ですか?
小野:ノバ・エンジニアリングは静岡県の小山町にあるんですけど、出版関係の仕事がしたいなと思って。そのためには東京に引っ越さないとなということで、たまたま見つけた仕事です(笑)。
長岡:でも、ちゃんと車関連ですね! なぜ編集の仕事が急にしたくなったんでしょう?
小野:イタリアにいたときに、モデナで自動車のフォトジャーナリストをしていたピーター・コルトリンの未亡人と知り合いまして。亡くなったピーターがどんな仕事をしていたかという話を聞くなかで、伝える仕事も面白いかなって思ったんですよね。なので、作るか伝える、どちらかの仕事がやりたいなと思っていました。
長岡:なるほど。両方の仕事をやってみて、どちらにするか決めていったのですね。
小野:いちばん好きなシトロエンって何ですか?
長岡:全部いいんですけど、「AMI 6」じゃないかなって思います。でも、「シトロエン・DS」もロマンチックだなと思いますね。イタリアに住んでいたら、日本で走っていないやつもいろいろ見られていますよね? そういうのはやっぱりいいなって思っちゃいます。
小野:使い倒されているシトロエンって愛おしくないですか?
長岡:いいですね。とってもいい!
小野:小さいシトロエンの「シトロエン・AX」とか、普通の人が普通に乗って、使い倒してスーパーにポンと置いてあるのとか、いいんですよね。
長岡:現地を感じますよね。僕もね、イギリスでボコボコになったDSがいたんですよ。それはそれでいいなって思っちゃいました。シトロエンってそういう“道具感”のある車ですよね。このあいだの撮影のときにも乗ってらっしゃった「シトロエン・C3」も、新しいけどもそういう匂いってまだあるなって感じがします。それがいいよなあ。
小野:そうですね。
小野は「海外で見た忘れられないシトロエンのある風景」として、パリで見かけた「シトロエン・DS」を挙げた。
小野:やっぱり、パリでDSを見かけるとハッとしますね。
長岡:ああ~!
小野:あるべきところにあるべき車が存在しているなと感じます。
長岡:(画として)整い過ぎているってことですね。
小野:写真を撮ろうとしても、まるで絵はがきのようになっちゃって撮る気がなくなるんですよね。
長岡:逆に面白くないってことですね(笑)。僕はマルセイユに行ったことがあって、山道をぶらぶら散歩していたら「シトロエン・メアリ」を見かけて。前の窓も倒して、天井もドアも窓も全部外したのに乗った、サングラスをかけたロン毛のおっちゃんが坂を下ってきたんです。そのときに「あ、フランスや!」と思ったんですよ。すごくいいなって思いましたね。
小野:そのときに大川さんが言っていたことが、自分のシトロエン観にすごく影響を与えました。大川さんは「車を通じて文化の地平を広げていく情熱があったのがシトロエンだ。その志の高さがアンドレ・シトロエンの魅力だ」みたいなことをおっしゃっていて、それがすごく印象に残っています。
長岡:なるほどなあ。そうでありつつも大衆のものでもあるわけだし、アイコニックで高級な、すごいものを作るわけではないってことですよね。そういうものが地平を広げていくってことでもあるかもしれませんね。みんなのものっていうか。
小野:そうですね。(先日の)取材のとき、AMIに4人ぐらいで乗って京都まで行ったみたいなお話をしてくださったじゃないですか。お話を聞いていて、体験を通じて世界を広げてくれる車って意味で、すごく価値があるなと思いましたね。
長岡:『カーグラフィック』のインタビューでも答えましたけど、シトロエンには言語化しづらいよさがあるんですよね。
小野:ここ5年ぐらいは世界中がEVシフトに動きましたが、思ったとおりにはいかなくて。そんななか、迷いながらの車作りがあって。激動を感じますね。
長岡:こんなに大きな過渡期はいままでなかったんじゃないかなって思いますよね。
小野:でも、乗る側からしたらどちらでもいいというか、自分をどこに連れて行ってくれるかのほうが大事で。あとは、何か自分に響くものに乗っていることのほうが大切で、何が正しい・悪いを気にして乗っていてもつまらないとは思うんですよね。
長岡:なるほど。
小野:そういう意味では、いまの若い世代の子たちが90年代の日本車に乗ったりして、シティ・ポップを聴いて、自分たちが生まれていない時代の空気感を楽しんでいたりするじゃないですか。ああいうもののほうが自然というか自由ですし、楽しんでくれているのはうれしく思いますね。
長岡:そうなんだよなあ。最先端を選ぶ人もいれば、自分の世界観で楽しんでいる人もいる。なかなか面白い時代とも言えますね。
小野:ガソリン、電気、ハイブリッドといくらでも選択肢がある。いい時代だなと思いますね。
『カーグラフィック』の最新情報は公式サイトまで。
東京都内のどこかにある特別な場所=「新しいカルチャーが生まれる場所」から長岡亮介がお届けする“大人の空間”を連想させるプログラム『CITROËN FOURGONNETTE』。放送は毎週土曜22時から。
小野さんが登場したのは、2025年12月20日(土)放送のJ-WAVE『CITROËN FOURGONNETTE』(ナビゲーター:長岡亮介)。ペトロールズの長岡が、心地よい音楽とともに、気の置けない仲間や時にはひとり語りで大人のライフスタイルを提案していく。
『カーグラフィック』最新号に長岡亮介と愛車が登場
株式会社カーグラフィックが発行する自動車雑誌『カーグラフィック』は、圧倒的なグラフィックとジャーナリストによる深い評論を特徴とし、新旧問わずさまざまな車を取り上げてきた。その世界観を映像で体現する番組『カーグラフィックTV』(BS朝日)も高い支持を集めている。2022年には創刊60周年という節目を迎えた。12月1日に発売された『カーグラフィック 2026年1月号』では、「フランス車の花と華」と題した特集を掲載。長岡は愛車である「シトロエン・AMI 6」とともに登場している。
長岡:このあいだ、特集の取材をしていただきまして、そのときに小野さんとご一緒しました。その節はありがとうございました。気持ちのいい天気の日でしたね。
小野:秋晴れでしたね。
長岡:『カーグラフィック』は日本の雑誌のなかでもかなりの歴史がありますよね。
小野:歴史のある雑誌で言うと、たとえば『モーターマガジン』さんがあるんですけども、2025年で70周年なんですね。『モーターマガジン』で働いていた高島鎮雄さんと、外部で協力されていた小林彰太郎が移籍されて作ったのが『カーグラフィック』です。
長岡:なるほど! 小野さんは編集長になってどれぐらいですか?
小野:2年目ですね。
長岡:雑誌の仕事をされるのは『カーグラフィック』が初めてですか?
小野:自動車だとそうですね。最初にミニカーやデザイン家電といったモノ系の雑誌をやっていました。
長岡:そうなんですか。車は昔からお好きとのことですが、『カーグラフィック』で実際にお仕事されてみてどうですか?
小野:責任感というか、看板が大きいので、それに恥じないものを作ろうという意識が勝ちますね。
長岡:『カーグラフィック』の真髄ってどこにあると感じますか?
小野:やっぱり実地、自分たちで取材することですね。特に昨今はそこを大事にしたいなと思っていて、海外も国内もできるだけ実際に触れて、人に会って取材をしたいです。
車を「作る側」から「伝える側」に移った理由は?
小野さんは高校卒業後にイタリアに留学し、約4年半をパドバとモデナで過ごして帰国。日本のレーシングチーム、ノバ・エンジニアリングで設計室に勤務したのち、国土交通省関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所で臨時事務官を勤める。その後、出版社を経て独立し、現在に至る。長岡:最初から順を追って聞きますね。まずイタリアには何をしに行ったのですか?
小野:パドバは語学留学で、モデナで自動車系のエンジニアリングの専門学校に通っていました。
長岡:すごい! なぜイタリアだったんですか?
小野:「イタリア車を作りたかった」という単純な理由です(笑)。
長岡:イタリアの車メーカーに入って設計をしたいという夢があったのですね。そのあとに帰国して、有名なノバ・エンジニアリングに入社された。F2の印象がありますが。
小野:F2やF3をやっていた時代もありましたが、(私が在籍していた頃は)スーパーGTを走らせたりしていました。あとは、直属の上司がF1解説でお馴染みの森脇基恭さんでした。
長岡:そうなんだ! ノバ・エンジニアリングでは何をされていたんですか?
小野:CAD/CAMですね。
長岡:図面を引いた車がレースを走っていたんですか?
小野:あとは、量産前のプロトタイプになったりしていました。
長岡:そして、国土交通省。こちらはどういった経緯ですか?
小野:ノバ・エンジニアリングは静岡県の小山町にあるんですけど、出版関係の仕事がしたいなと思って。そのためには東京に引っ越さないとなということで、たまたま見つけた仕事です(笑)。
長岡:でも、ちゃんと車関連ですね! なぜ編集の仕事が急にしたくなったんでしょう?
小野:イタリアにいたときに、モデナで自動車のフォトジャーナリストをしていたピーター・コルトリンの未亡人と知り合いまして。亡くなったピーターがどんな仕事をしていたかという話を聞くなかで、伝える仕事も面白いかなって思ったんですよね。なので、作るか伝える、どちらかの仕事がやりたいなと思っていました。
長岡:なるほど。両方の仕事をやってみて、どちらにするか決めていったのですね。
使い古されたシトロエンに感じる魅力
続いてふたりは、フランスの自動車ブランド、シトロエンについて語り合う。小野:いちばん好きなシトロエンって何ですか?
長岡:全部いいんですけど、「AMI 6」じゃないかなって思います。でも、「シトロエン・DS」もロマンチックだなと思いますね。イタリアに住んでいたら、日本で走っていないやつもいろいろ見られていますよね? そういうのはやっぱりいいなって思っちゃいます。
小野:使い倒されているシトロエンって愛おしくないですか?
長岡:いいですね。とってもいい!
小野:小さいシトロエンの「シトロエン・AX」とか、普通の人が普通に乗って、使い倒してスーパーにポンと置いてあるのとか、いいんですよね。
長岡:現地を感じますよね。僕もね、イギリスでボコボコになったDSがいたんですよ。それはそれでいいなって思っちゃいました。シトロエンってそういう“道具感”のある車ですよね。このあいだの撮影のときにも乗ってらっしゃった「シトロエン・C3」も、新しいけどもそういう匂いってまだあるなって感じがします。それがいいよなあ。
小野:そうですね。
小野は「海外で見た忘れられないシトロエンのある風景」として、パリで見かけた「シトロエン・DS」を挙げた。
小野:やっぱり、パリでDSを見かけるとハッとしますね。
長岡:ああ~!
小野:あるべきところにあるべき車が存在しているなと感じます。
長岡:(画として)整い過ぎているってことですね。
小野:写真を撮ろうとしても、まるで絵はがきのようになっちゃって撮る気がなくなるんですよね。
長岡:逆に面白くないってことですね(笑)。僕はマルセイユに行ったことがあって、山道をぶらぶら散歩していたら「シトロエン・メアリ」を見かけて。前の窓も倒して、天井もドアも窓も全部外したのに乗った、サングラスをかけたロン毛のおっちゃんが坂を下ってきたんです。そのときに「あ、フランスや!」と思ったんですよ。すごくいいなって思いましたね。
シトロエンとは「文化の地平を広げる存在」
シトロエンが創立100周年を迎えた2019年、フリーで活動していた小野さんは『カーグラフィック』の仕事を引き受け、自動車雑誌『NAVI』の創刊者である大川 悠さんへのインタビューを担当したという。小野:そのときに大川さんが言っていたことが、自分のシトロエン観にすごく影響を与えました。大川さんは「車を通じて文化の地平を広げていく情熱があったのがシトロエンだ。その志の高さがアンドレ・シトロエンの魅力だ」みたいなことをおっしゃっていて、それがすごく印象に残っています。
長岡:なるほどなあ。そうでありつつも大衆のものでもあるわけだし、アイコニックで高級な、すごいものを作るわけではないってことですよね。そういうものが地平を広げていくってことでもあるかもしれませんね。みんなのものっていうか。
小野:そうですね。(先日の)取材のとき、AMIに4人ぐらいで乗って京都まで行ったみたいなお話をしてくださったじゃないですか。お話を聞いていて、体験を通じて世界を広げてくれる車って意味で、すごく価値があるなと思いましたね。
長岡:『カーグラフィック』のインタビューでも答えましたけど、シトロエンには言語化しづらいよさがあるんですよね。
多様化した車が数多くある現代は「いい時代」
さまざまなコンセプトのもとに生み出され、最先端の技術を搭載した車は、その時代の価値観や思想を映し出す存在である。長岡は小野さんに「仕事をされていくなかで時代の移り変わりを感じることはありますか?」と問いかける。小野:ここ5年ぐらいは世界中がEVシフトに動きましたが、思ったとおりにはいかなくて。そんななか、迷いながらの車作りがあって。激動を感じますね。
長岡:こんなに大きな過渡期はいままでなかったんじゃないかなって思いますよね。
小野:でも、乗る側からしたらどちらでもいいというか、自分をどこに連れて行ってくれるかのほうが大事で。あとは、何か自分に響くものに乗っていることのほうが大切で、何が正しい・悪いを気にして乗っていてもつまらないとは思うんですよね。
長岡:なるほど。
小野:そういう意味では、いまの若い世代の子たちが90年代の日本車に乗ったりして、シティ・ポップを聴いて、自分たちが生まれていない時代の空気感を楽しんでいたりするじゃないですか。ああいうもののほうが自然というか自由ですし、楽しんでくれているのはうれしく思いますね。
長岡:そうなんだよなあ。最先端を選ぶ人もいれば、自分の世界観で楽しんでいる人もいる。なかなか面白い時代とも言えますね。
小野:ガソリン、電気、ハイブリッドといくらでも選択肢がある。いい時代だなと思いますね。
『カーグラフィック』の最新情報は公式サイトまで。
東京都内のどこかにある特別な場所=「新しいカルチャーが生まれる場所」から長岡亮介がお届けする“大人の空間”を連想させるプログラム『CITROËN FOURGONNETTE』。放送は毎週土曜22時から。
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。
番組情報
- CITROËN FOURGONNETTE
-
毎週土曜22:00-22:54
-
長岡亮介










