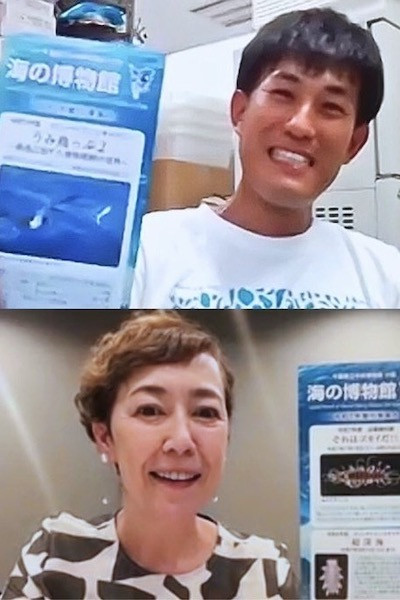俳優の永瀬正敏が、映画監督の相米慎二やジム・ジャームッシュとのエピソードや、想いを語った。
永瀬が登場したのは、クリス智子がお届けする『TALK TO NEIGHBORS』。この番組は毎週ひと組、クリスがいま声を届けたい人を迎える30分のトークプログラムだ。月曜から木曜はラジオでオンエアされ、翌金曜には放送された内容に加えて、限定トークも含むポッドキャストが配信される。
ここでは、10月21日(火)にオンエアしたトーク内容をテキストでお届けする。
・ポッドキャストページ
クリス:この本は想像以上に深い1冊で、10月に公開した映画『おーい、応為』の撮影への臨み方とか、その当時のこととか経緯とか、各映画に対していろいろと語っていますよね。
クリス:この本の中で、30代ごろまでは(自分を)俯瞰して見ることがなかなか難しかったというようなことが書かれてましたね。
永瀬:はい、そうです。
クリス:10代のときに相米慎二監督作品『ションベン・ライダー』(1983年)でデビューして。これは高校生でしたよね?
永瀬:高1の夏休みに撮ってましたね。若いころは自分の役で手一杯というか、自分の役に集中することしかできなくて。でも、ある時期はそういうパワーも必要かなって思うんですけど。しばらくしてくると、映画ってみんなで作っていくものだから、いろんな人との関わり合いだったりキャッチボールだったりを監督の世界の中でやらせていただいているっていうことがわかるというか。だから、「これ」って決め込むよりは、もうちょっと広い視野で見てやっていくほうがいいな、そっちのほうが楽しいなっていうふうに思い始めて。それはテレビドラマで探偵をやってたころなんですけど。
クリス:『私立探偵 濱マイク』ですよね。
永瀬:そうです。もともと、林 海象監督が作られた世界観だったんですけど、ドラマの立ち上げのタイミングでちょうど監督がアメリカに留学されていて、「濱マイク」のことをよく知ってる人が少なかったんですよね。僕とプロデューサーさんくらいで。それで自分がちょっとスタッフ側にまわっている時期でもあって、そこでいろんな大変さがわかったりとか、現場の進め方も学んだりして、そういうのもよかった気がしますね。
永瀬:監督に演出をつけられても、当時はど素人で、演技の勉強もしたことがなかったですし、映画もそんなに観たことがない僕にそういう演出をしても無理だって、監督はわかってたんだと思うんですよね。だから、自然に何度もやっていって、いろんなものが剥がれ落ちたあとに本物が見えてくるっていうんですかね。だから、いくら訊きにいっても「そんなこと俺が知るか」「お前が演じてるんだから、お前がいちばん知ってるはずだろ」って言われて。
クリス:すごいですね。そう言われるといろいろ考えちゃいますよね。
永瀬:でも、そこが基本になってしまったので。
クリス:この本『NAGASE Nagase Stands On That Landある俳優に関する考察』にもありますけど、『ションベン・ライダー』のときは道端でいきなり歌わされたんでしたっけ?
永瀬:そうです。ちょうど出勤ラッシュのときの駅前で歌って踊らされて。始めるとスタッフの人たちが遠くへ散っていくんですよ。子どもたちだけで歌って踊って。めちゃめちゃ恥ずかしいんですよ。あと、まったく無視されるので。でも、途中からやけくそになってくるんですよね。それは羞恥心を外す作業で、それをしていただいて……。まぁ、いま思えばですけどね。
クリス:たしかに。
永瀬:当時は「何やらされてるんだ?」って思ってましたけど、いま思えば本当に財産だと思いますね。相米さんは天国に行ってしまったので。僕の永遠の映画のお師匠さんだし、先生だと思っているので、毎日、天国に問いかけるんですけど、答えをなかなか返してくれないもので。でも、それをずっと抱えているっていうのも何かひとつ、役者を続けていくうえでの大切なものなのかなって思ったりしますけどね。
クリス:相米監督ともうおひとり、永瀬さんの活動初期に欠かせないのは、やはりジム・ジャームッシュ監督がいらっしゃって。
永瀬:そうですね。大恩人のひとりですね。映画の現場になかなか行けない時期があって。テレビドラマですごくいろんなことを教わったりしてお世話になってたんです。無駄な期間だったとは思わないけど、デビューが映画なので、また映画をやりたいなって思ってるときに映画界に連れ戻してくれた人がジャームッシュ監督だったんですよね。
クリス:随分、遠いところから連れ戻してくれましたね。
永瀬:だいぶ手が長いっていうかね(笑)。
クリス:そのころのオーディションの話などもこの本にはあって、非常に面白かったです。『ミステリー・トレイン』も観直しちゃいました。色あせてない。そして永瀬さんが若い。少年ですよね。
永瀬:若いですよね。
クリス:作品はオムニバス形式で、最初のパートで工藤夕貴さんと永瀬さんのふたりがメンフィスに行くというストーリーで。
永瀬:そうですね。ジャームッシュ監督とはそれからも友人関係っていうとおこがましい気がしますけど、彼もそう言ってくれている関係が続いていて。僕がアメリカに行くときは必ず連絡をくれて会ったりとか、メールのやり取りとかはしていたんですけど、そういうふうに長く付き合えると思ってもみなかったので。それこそ人生の財産をいただいたっていうか。めちゃくちゃいい人なんですよ。
クリス:この本で、ジャームッシュ監督の現場の様子を読めば読むほど、なんて鑑(かがみ)のような人なんだと。
永瀬:本当にそうなんですよ。
クリス:自ら率先していろいろやられたり、エキストラに至るまで自分でスカウトされるという。
永瀬:しかも、現場ではみんなが平等なんですよね。すごくいい現場を作られる監督ですね。
クリス:『パターソン』でひさしぶりにご一緒されていますけど、そこで関係の変化はあったんですか。
永瀬:あんまりない気がしますね。それがありがたい気もちょっとします。好きな音楽とか好きなものがお互いに似てたっていうのもあるんでしょうけど、彼も永遠の少年というか、映画が好きで音楽が好きでっていうところがあって。いまや世界的な大巨匠の監督ですけど、そういうそぶりが一切ないというか。
クリス:きっと最初からお互いの関係性がそうだったんでしょうね。『パターソン』もいい映画でしたよね。
永瀬:自分は最後にちょこっと出てるんですけど、本当に好きな映画でしたね。まず台本を送っていただいて読んだときに、バスの運転手と奥さんのふたりのなんでもない1週間の話なんだけど、それをどう映画にするんだろうなって思ってたんですよね。それを素晴らしい作品に仕上げられて。映画の時間軸のなかの機微みたいな、大きなアクションがないなかで、お客さんに2時間観せるって相当な力量がないとできないので、すごい監督だなって思いましたね。
その後、永瀬は日本だけでなく海外の作品にも多く携わり、現地の現場で日本との違いを感じたという。
永瀬:海外の人たちからは意見を求められることが多い気がしますね。そのアイデアのストックがないと「はい、わかりました」っていうふうになってしまう気がしますね。
クリス:その始まりが『ミステリー・トレイン』として、それ以降もそういうことに応えていこうって気持ちがあったんですか?
永瀬:それはジャームッシュさんがよかったんですかね。撮影の1週間くらい前かな。ずっとリハーサルをしてるときに、毎日、毎シーン、アイデアを訊いてくれるんですよね。「僕はこう書いてるけど、もっと面白いアイデアはないかな」っていう。それでいろんなもの出して。あと、アジアの国々をまわって撮影をするときも、「もっとこういうのないでしょうか」「アイデアはないかな」みたいなのをよく訊かれたりしていて、それをパッと言えるストックを持っていなきゃダメなのかなって、そのころから思ってましたから。
クリス:脚本があったとしても、それを生身のものにするのは俳優さんの身体になるわけだから……相米監督の言葉に戻っちゃいますね。「自分で考えろ」って。
永瀬:そうなんですよね。いくらキャリアを積んでも、毎回、必ずそこに戻ってる気がしますね。
永瀬正敏の最新情報は Instagram公式アカウント(@masatoshi_nagase_official)まで。
クリス智子がお届けする『TALK TO NEIGHBORS』は、J-WAVEで月曜〜木曜の13時よりオンエア。ポッドキャストでも配信中。
・ポッドキャスト限定のエピソードはこちらから
永瀬が登場したのは、クリス智子がお届けする『TALK TO NEIGHBORS』。この番組は毎週ひと組、クリスがいま声を届けたい人を迎える30分のトークプログラムだ。月曜から木曜はラジオでオンエアされ、翌金曜には放送された内容に加えて、限定トークも含むポッドキャストが配信される。
ここでは、10月21日(火)にオンエアしたトーク内容をテキストでお届けする。
・ポッドキャストページ
若いころは自分の役で手一杯だった
永瀬が歩んだ“海外作品”と“インターナショナルな作品”について、永瀬自身が「ひとりがたり」をした書籍『NAGASE Nagase Stands On That Landある俳優に関する考察』(A PEOPLE)が7月に発売された。クリス:この本は想像以上に深い1冊で、10月に公開した映画『おーい、応為』の撮影への臨み方とか、その当時のこととか経緯とか、各映画に対していろいろと語っていますよね。
『おーい、応為』10.17 Fri [本予告] 長澤まさみ×髙橋海人×永瀬正敏
クリス:この本の中で、30代ごろまでは(自分を)俯瞰して見ることがなかなか難しかったというようなことが書かれてましたね。
永瀬:はい、そうです。
クリス:10代のときに相米慎二監督作品『ションベン・ライダー』(1983年)でデビューして。これは高校生でしたよね?
永瀬:高1の夏休みに撮ってましたね。若いころは自分の役で手一杯というか、自分の役に集中することしかできなくて。でも、ある時期はそういうパワーも必要かなって思うんですけど。しばらくしてくると、映画ってみんなで作っていくものだから、いろんな人との関わり合いだったりキャッチボールだったりを監督の世界の中でやらせていただいているっていうことがわかるというか。だから、「これ」って決め込むよりは、もうちょっと広い視野で見てやっていくほうがいいな、そっちのほうが楽しいなっていうふうに思い始めて。それはテレビドラマで探偵をやってたころなんですけど。
クリス:『私立探偵 濱マイク』ですよね。
永瀬:そうです。もともと、林 海象監督が作られた世界観だったんですけど、ドラマの立ち上げのタイミングでちょうど監督がアメリカに留学されていて、「濱マイク」のことをよく知ってる人が少なかったんですよね。僕とプロデューサーさんくらいで。それで自分がちょっとスタッフ側にまわっている時期でもあって、そこでいろんな大変さがわかったりとか、現場の進め方も学んだりして、そういうのもよかった気がしますね。
出勤ラッシュの駅前で歌って踊らされて…
永瀬のデビュー作である『ションベン・ライダー』を手がけた相米監督は、出会ったころから「自分で考えろ」というスタンスだったと、永瀬は振り返る。永瀬:監督に演出をつけられても、当時はど素人で、演技の勉強もしたことがなかったですし、映画もそんなに観たことがない僕にそういう演出をしても無理だって、監督はわかってたんだと思うんですよね。だから、自然に何度もやっていって、いろんなものが剥がれ落ちたあとに本物が見えてくるっていうんですかね。だから、いくら訊きにいっても「そんなこと俺が知るか」「お前が演じてるんだから、お前がいちばん知ってるはずだろ」って言われて。
クリス:すごいですね。そう言われるといろいろ考えちゃいますよね。
永瀬:でも、そこが基本になってしまったので。
クリス:この本『NAGASE Nagase Stands On That Landある俳優に関する考察』にもありますけど、『ションベン・ライダー』のときは道端でいきなり歌わされたんでしたっけ?
永瀬:そうです。ちょうど出勤ラッシュのときの駅前で歌って踊らされて。始めるとスタッフの人たちが遠くへ散っていくんですよ。子どもたちだけで歌って踊って。めちゃめちゃ恥ずかしいんですよ。あと、まったく無視されるので。でも、途中からやけくそになってくるんですよね。それは羞恥心を外す作業で、それをしていただいて……。まぁ、いま思えばですけどね。
クリス:たしかに。
永瀬:当時は「何やらされてるんだ?」って思ってましたけど、いま思えば本当に財産だと思いますね。相米さんは天国に行ってしまったので。僕の永遠の映画のお師匠さんだし、先生だと思っているので、毎日、天国に問いかけるんですけど、答えをなかなか返してくれないもので。でも、それをずっと抱えているっていうのも何かひとつ、役者を続けていくうえでの大切なものなのかなって思ったりしますけどね。
ジム・ジャームッシュ監督が、映画界に連れ戻してくれた
続いて、永瀬の役者人生に欠かせないジム・ジャームッシュ監督の話に。永瀬はジム・ジャームッシュ監督作品『ミステリー・トレイン』(1989年)に出演した。クリス:相米監督ともうおひとり、永瀬さんの活動初期に欠かせないのは、やはりジム・ジャームッシュ監督がいらっしゃって。
永瀬:そうですね。大恩人のひとりですね。映画の現場になかなか行けない時期があって。テレビドラマですごくいろんなことを教わったりしてお世話になってたんです。無駄な期間だったとは思わないけど、デビューが映画なので、また映画をやりたいなって思ってるときに映画界に連れ戻してくれた人がジャームッシュ監督だったんですよね。
クリス:随分、遠いところから連れ戻してくれましたね。
永瀬:だいぶ手が長いっていうかね(笑)。
クリス:そのころのオーディションの話などもこの本にはあって、非常に面白かったです。『ミステリー・トレイン』も観直しちゃいました。色あせてない。そして永瀬さんが若い。少年ですよね。
永瀬:若いですよね。
クリス:作品はオムニバス形式で、最初のパートで工藤夕貴さんと永瀬さんのふたりがメンフィスに行くというストーリーで。
永瀬:そうですね。ジャームッシュ監督とはそれからも友人関係っていうとおこがましい気がしますけど、彼もそう言ってくれている関係が続いていて。僕がアメリカに行くときは必ず連絡をくれて会ったりとか、メールのやり取りとかはしていたんですけど、そういうふうに長く付き合えると思ってもみなかったので。それこそ人生の財産をいただいたっていうか。めちゃくちゃいい人なんですよ。
クリス:この本で、ジャームッシュ監督の現場の様子を読めば読むほど、なんて鑑(かがみ)のような人なんだと。
永瀬:本当にそうなんですよ。
クリス:自ら率先していろいろやられたり、エキストラに至るまで自分でスカウトされるという。
永瀬:しかも、現場ではみんなが平等なんですよね。すごくいい現場を作られる監督ですね。
毎日、毎シーン、アイデアを訊いてくれた
そして永瀬は、2016年に『パターソン』で約27年ぶりにジャームッシュ監督の作品に出演した。『パターソン』本予告 8/26(土)公開
永瀬:あんまりない気がしますね。それがありがたい気もちょっとします。好きな音楽とか好きなものがお互いに似てたっていうのもあるんでしょうけど、彼も永遠の少年というか、映画が好きで音楽が好きでっていうところがあって。いまや世界的な大巨匠の監督ですけど、そういうそぶりが一切ないというか。
クリス:きっと最初からお互いの関係性がそうだったんでしょうね。『パターソン』もいい映画でしたよね。
永瀬:自分は最後にちょこっと出てるんですけど、本当に好きな映画でしたね。まず台本を送っていただいて読んだときに、バスの運転手と奥さんのふたりのなんでもない1週間の話なんだけど、それをどう映画にするんだろうなって思ってたんですよね。それを素晴らしい作品に仕上げられて。映画の時間軸のなかの機微みたいな、大きなアクションがないなかで、お客さんに2時間観せるって相当な力量がないとできないので、すごい監督だなって思いましたね。
その後、永瀬は日本だけでなく海外の作品にも多く携わり、現地の現場で日本との違いを感じたという。
永瀬:海外の人たちからは意見を求められることが多い気がしますね。そのアイデアのストックがないと「はい、わかりました」っていうふうになってしまう気がしますね。
クリス:その始まりが『ミステリー・トレイン』として、それ以降もそういうことに応えていこうって気持ちがあったんですか?
永瀬:それはジャームッシュさんがよかったんですかね。撮影の1週間くらい前かな。ずっとリハーサルをしてるときに、毎日、毎シーン、アイデアを訊いてくれるんですよね。「僕はこう書いてるけど、もっと面白いアイデアはないかな」っていう。それでいろんなもの出して。あと、アジアの国々をまわって撮影をするときも、「もっとこういうのないでしょうか」「アイデアはないかな」みたいなのをよく訊かれたりしていて、それをパッと言えるストックを持っていなきゃダメなのかなって、そのころから思ってましたから。
クリス:脚本があったとしても、それを生身のものにするのは俳優さんの身体になるわけだから……相米監督の言葉に戻っちゃいますね。「自分で考えろ」って。
永瀬:そうなんですよね。いくらキャリアを積んでも、毎回、必ずそこに戻ってる気がしますね。
永瀬正敏の最新情報は Instagram公式アカウント(@masatoshi_nagase_official)まで。
クリス智子がお届けする『TALK TO NEIGHBORS』は、J-WAVEで月曜〜木曜の13時よりオンエア。ポッドキャストでも配信中。
・ポッドキャスト限定のエピソードはこちらから
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。
番組情報
- TALK TO NEIGHBORS
-
月・火・水・木曜13:00-13:30
-
クリス智子