
(ケーブル延暦寺駅から見た大津市街の眺め/画像素材:PIXTA)
滋賀・大津市坂本に関する歴史や魅力、独自の風習について、作家・文献学者の山口謠司さんが語った。
この内容をお届けしたのは、J-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』内のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE」。放送日は2025年6月16日(月)〜6月19日(木)。同コーナーでは、独自の文化のなかで育まれてきた“日本ならではの知恵”を、山口さんが解説する。ここではその内容をテキストで紹介。
また、ポッドキャストでも過去のオンエアをアーカイブとして配信している。山口さんが実際に大津市坂本を訪れ、そこに暮らす人から聞いたエピソードの詳細が楽しめる。
・ポッドキャストページ
山口:大津市坂本を訪れると、若い女性2人組や、お母様とお嬢様の組み合わせなど、女性2人組が日吉大社に参っていました。
深い森のやわらかい神聖な空気が、このお宮を包んでいました。そんな環境だったせいか、僕の秘書は車の中で気持ちよさそうに寝ていましたが、僕は車から飛び出た瞬間、「ここはなんて気が澄んでいるんだろう」と感じ、全ての神様のお社にお祈りをしてきました。
そのうちのひとつの神様が白山宮の菊理媛神(くくりひめのかみ)。「くくりひめのかみ」という響きが可愛すぎて、一度聞いたら忘れられませんが、菊理媛神は、828年に大津の日吉大社に石川県白山比咩神社より降臨されたそうです。
 山口:菊理媛神は、伊邪那岐(いざなぎ)と伊邪那美(いざなみ)の争いを仲裁した伝承から、男女の縁を取り持つ縁結びの神様として知られています。
伊邪那美の神様がお亡くなりになって、黄泉の国に行かれてしまうわけですが、これを追ってご主人の伊邪那岐の神様が「帰ってきて、伊邪那美」と追いかけていくわけです。そのとき、伊邪那美は「決して私の姿を見てはいけない」と言われたそうです。しかし男はバカですからを見てしまったんですね。
山口:菊理媛神は、伊邪那岐(いざなぎ)と伊邪那美(いざなみ)の争いを仲裁した伝承から、男女の縁を取り持つ縁結びの神様として知られています。
伊邪那美の神様がお亡くなりになって、黄泉の国に行かれてしまうわけですが、これを追ってご主人の伊邪那岐の神様が「帰ってきて、伊邪那美」と追いかけていくわけです。そのとき、伊邪那美は「決して私の姿を見てはいけない」と言われたそうです。しかし男はバカですからを見てしまったんですね。
見てはいけないものを見てしまったということで、伊邪那美は伊邪那岐を怒ったそうですが、そこに菊理媛神が現れて「やめなさい。怒ったりするのはよくないわよ。男はバカだから振り返ってしまったのです」と仲裁しました。そんなふたりの間を取り直したということで、菊理媛神はふたりの間を繋ぎ止めてくれる神様として祀られるようになったそうです。
 山口さんは坂本比叡山口駅から徒歩約3分の位置にある蕎麦屋を訪れた。「鶴喜」というお店で、「ずっと行ってみたかった」と語る。
山口さんは坂本比叡山口駅から徒歩約3分の位置にある蕎麦屋を訪れた。「鶴喜」というお店で、「ずっと行ってみたかった」と語る。
山口:司馬遼太郎さんがお書きになられた『街道をゆく』という随筆の中で、「大津の坂本を訪れた際、『鶴喜』の隣の蕎麦屋に行ってしまって、『鶴喜』には行けなかった」という話があり、それが全国に広がったようで、“司馬遼太郎は「鶴喜」に行ったことがない”ということが定説となっているみたいです。しかし、「鶴喜」のご主人に聞いたところ「司馬さんはよく来ていましたよ」と仰いました。
「鶴喜」は随筆家の白洲正子さんもお好きでかつてよく来られていたそうです。昔からある有名なお蕎麦屋さんで、鶴喜の女将・上延慶子さんから「白洲さんはここにお座りになっていましたよ」など色々お話しが聞けました。
 山口:延暦寺は、788年に天台宗の開祖である最澄によって薬師如来を本尊として建てられたお寺です。
山口:延暦寺は、788年に天台宗の開祖である最澄によって薬師如来を本尊として建てられたお寺です。
奈良時代の仏教では、“何回も何回も生まれ変わらないと仏様にはなれない”と言われていましたが、最澄は「そんなことはない。人は生まれながらして、菩薩(ぼさつ)であり悟りを開くことができるもの」と説いたのです。
自らを超越するために最澄が自分に課した修行は、12年間、山に登ったら山から降りないで苦しさの中から悟りを見つけないといけないというものだった。
山口:現在12代目の鶴喜のご主人は、子供の頃、お父様が毎朝、比叡山延暦寺まで徒歩で4時間かけて、修行をされる僧侶の方々のために、ものすごく重たい食事を持って、上がっていたのを目にしていたそうです。
 「今は道ができているので、軽トラックで向かえば楽なんです」と仰っていましたが、おかもち(料理や食器などを運ぶための箱や桶のこと)が飾ってあって、僕にはとても抱えきれないような重たいものでした。300年以上使われたというおかもちです。
「今は道ができているので、軽トラックで向かえば楽なんです」と仰っていましたが、おかもち(料理や食器などを運ぶための箱や桶のこと)が飾ってあって、僕にはとても抱えきれないような重たいものでした。300年以上使われたというおかもちです。
最盛期には2000〜3000人も修行するお坊さんがいたそうだ。
山口:その人たちのために毎日、お料理を作って運んで、そして降ろしてということをやっていらっしゃったんです。
延暦寺には100日間の五穀断ちや千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)など、命をかけた厳しい修行をしている方たちがいらっしゃり、修行を終えた人たちに元気になってもらう栄養としてお蕎麦が珍重されていたのです。鶴は1000年と言われていますが、鶴喜のお蕎麦をいただかれると、長寿になるのかもしれません。
鶴喜のお庭は美しく、琵琶湖でとれたアマゴのお煮付けもとってもおいしかったです。ついついお蕎麦を大盛りにして、お腹いっぱいになってしまいました。坂本はいいところがたくさんありすぎて、一回では話し切れないです。また訪れて、頭を整理してきます。

山口:この楽曲は土木工事をお仕事とするお母さんを描いた作品です。お母さんが一生懸命、男の人に負けないように力を発揮して頑張っている。いじめられた自分が泣きながら帰っている途中、お母さんが子供のためにエンヤコラと働いている。そんな姿を見て、今度は涙を堪えて、「勉強するよ」と誓うのです。
ところで僕は石が大好きです。山や川、海に行くと石を探します。もしかしたら大切な文化財の一部かもしれないので、石を持って帰るときは注意をしますが、触ったり、握ったり、眺めてみたり。石っていろんなことを考えさせてくれるんですね。
山口さんは「穴太衆(あのうしゅう)」の話をしてくれた。
山口:京阪電車石山坂本線・終点の坂本比叡山口駅で降りると、正面に大きな看板が建っています。「世界文化遺産比叡山延暦寺」と「穴太衆積み門前町坂本」というもの。石を積むことを専門にした人がいらっしゃったところですね。
 古く弥生時代、稲作をするためには水田を用意しなければなりませんでした。山から流れてくる水を溜めて水田にしますが、坂本という地名の通り、ここは比叡山から琵琶湖まで、土地が斜めになっています。
古く弥生時代、稲作をするためには水田を用意しなければなりませんでした。山から流れてくる水を溜めて水田にしますが、坂本という地名の通り、ここは比叡山から琵琶湖まで、土地が斜めになっています。
斜めになった土地を平にするために、石積みをして水田を作ります。日本国中の棚田はほとんどこうやって石積みをして、作られていましたが、この技術がさらに進化し、姫路城・大阪城・犬山城・岐阜城・松本城、そして江戸城の基礎を支える石垣が作り上げられました。作業したのが、坂本の穴太衆と呼ばれる方々だったのです。
この穴太衆は石を積み上げてドームを作ることができたそうだ。
山口:坂本の石垣を作る専門技術を持った人たちは、6世紀半ばから日本のほかの地域では見られない、古墳と横穴式石室を作っていました。石を積み上げてドームを作ることができた人たちなんです。
これはどういうことかと言うと、シベリアとかアラスカ、あるいはカナダ、グリーンランドのイヌイットの方々が氷の家「イグルー」を作るのと同じように、石を集めて型を整えてドームを作るのです。
それから韓国の伝統的な床暖房システム「オンドル」を、大きな石板を床下に敷いて作っていたことも確認されています。これらの技術が比叡山延暦寺の開山とともに山の上に持って行かれて、塔や石垣を作ることに応用されました。
坂本駅のそばには美しい石垣で囲まれた日本最古の茶園がある。
山口:この茶園の歴史を辿れば、唐へ留学した最澄が持ち帰ってきたお茶の種で育ったものだそうです。
最澄は空海の弟子でもありました。ですが「お前には才能がない!」と破門状受け取ることになります。そのとき、最澄は空海に対し「申し訳ありませんでした。私が悪かったです」と自分の非を詫びた手紙を送るときに、お茶を10斤(約6kg)送ったといわれています。
 一服のお茶を大切な人といただく時間。茶道ではこういうことを「一期一会」と言いますが、穴太衆が積み上げた石垣の上で大事に育てられてきたお茶、そして今も残る田んぼで作られたお米の一粒一粒……伝統、あるいは文化というものは長い時間の人々の汗と苦労の末の作品に違いありません。
一服のお茶を大切な人といただく時間。茶道ではこういうことを「一期一会」と言いますが、穴太衆が積み上げた石垣の上で大事に育てられてきたお茶、そして今も残る田んぼで作られたお米の一粒一粒……伝統、あるいは文化というものは長い時間の人々の汗と苦労の末の作品に違いありません。
穴太衆が積む石垣の技術は世界でも非常に注目されています。米国・テキサス州のダラスにある「ロレックスタワー」。ものすごく大きな建物ですが、これを支えているのが穴太衆の人たちが積んだ石垣と言われています。
『ヨイトマケの唄』の歌詞を引用させてもらうなら<世界のためならエンヤコラ>といったところでしょうか。
ひとつひとつ石を積んでいく。人生も石垣のようなものなのかもしれませんね。みんな一生懸命、頑張りましょう!
(構成=中山洋平)
この内容をお届けしたのは、J-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』内のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE」。放送日は2025年6月16日(月)〜6月19日(木)。同コーナーでは、独自の文化のなかで育まれてきた“日本ならではの知恵”を、山口さんが解説する。ここではその内容をテキストで紹介。
また、ポッドキャストでも過去のオンエアをアーカイブとして配信している。山口さんが実際に大津市坂本を訪れ、そこに暮らす人から聞いたエピソードの詳細が楽しめる。
・ポッドキャストページ
2人の間を繋ぎ止めてくれる神様
滋賀県大津市の坂本は、比叡山の東麓、および琵琶湖の南西岸に位置しており、「比叡山延暦寺」や「日吉大社」を擁する門前町として有名だ。石積みがもたらす趣深い街並みを楽しむことができる。山口:大津市坂本を訪れると、若い女性2人組や、お母様とお嬢様の組み合わせなど、女性2人組が日吉大社に参っていました。
深い森のやわらかい神聖な空気が、このお宮を包んでいました。そんな環境だったせいか、僕の秘書は車の中で気持ちよさそうに寝ていましたが、僕は車から飛び出た瞬間、「ここはなんて気が澄んでいるんだろう」と感じ、全ての神様のお社にお祈りをしてきました。
そのうちのひとつの神様が白山宮の菊理媛神(くくりひめのかみ)。「くくりひめのかみ」という響きが可愛すぎて、一度聞いたら忘れられませんが、菊理媛神は、828年に大津の日吉大社に石川県白山比咩神社より降臨されたそうです。

この菊理媛神はご縁を繋いでくださる神様だ。
見てはいけないものを見てしまったということで、伊邪那美は伊邪那岐を怒ったそうですが、そこに菊理媛神が現れて「やめなさい。怒ったりするのはよくないわよ。男はバカだから振り返ってしまったのです」と仲裁しました。そんなふたりの間を取り直したということで、菊理媛神はふたりの間を繋ぎ止めてくれる神様として祀られるようになったそうです。
大津・坂本にある老舗蕎麦屋さん

山口:司馬遼太郎さんがお書きになられた『街道をゆく』という随筆の中で、「大津の坂本を訪れた際、『鶴喜』の隣の蕎麦屋に行ってしまって、『鶴喜』には行けなかった」という話があり、それが全国に広がったようで、“司馬遼太郎は「鶴喜」に行ったことがない”ということが定説となっているみたいです。しかし、「鶴喜」のご主人に聞いたところ「司馬さんはよく来ていましたよ」と仰いました。
「鶴喜」は随筆家の白洲正子さんもお好きでかつてよく来られていたそうです。昔からある有名なお蕎麦屋さんで、鶴喜の女将・上延慶子さんから「白洲さんはここにお座りになっていましたよ」など色々お話しが聞けました。

上延さんいわく「鶴喜」は「延暦寺に登ることが許された唯一のお料理屋さんだった」そうだ。
奈良時代の仏教では、“何回も何回も生まれ変わらないと仏様にはなれない”と言われていましたが、最澄は「そんなことはない。人は生まれながらして、菩薩(ぼさつ)であり悟りを開くことができるもの」と説いたのです。
自らを超越するために最澄が自分に課した修行は、12年間、山に登ったら山から降りないで苦しさの中から悟りを見つけないといけないというものだった。
山口:現在12代目の鶴喜のご主人は、子供の頃、お父様が毎朝、比叡山延暦寺まで徒歩で4時間かけて、修行をされる僧侶の方々のために、ものすごく重たい食事を持って、上がっていたのを目にしていたそうです。

最盛期には2000〜3000人も修行するお坊さんがいたそうだ。
山口:その人たちのために毎日、お料理を作って運んで、そして降ろしてということをやっていらっしゃったんです。
延暦寺には100日間の五穀断ちや千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)など、命をかけた厳しい修行をしている方たちがいらっしゃり、修行を終えた人たちに元気になってもらう栄養としてお蕎麦が珍重されていたのです。鶴は1000年と言われていますが、鶴喜のお蕎麦をいただかれると、長寿になるのかもしれません。
鶴喜のお庭は美しく、琵琶湖でとれたアマゴのお煮付けもとってもおいしかったです。ついついお蕎麦を大盛りにして、お腹いっぱいになってしまいました。坂本はいいところがたくさんありすぎて、一回では話し切れないです。また訪れて、頭を整理してきます。

石を積み上げてドームを作る…職人たちの技術
<父ちゃんのためなら エンヤコラ/母ちゃんのためなら エンヤコラ> 美輪明宏が自らが作詞・作曲した楽曲『ヨイトマケの唄』の歌詞だ。シングルレコード発売されたのは1965年7月。山口:この楽曲は土木工事をお仕事とするお母さんを描いた作品です。お母さんが一生懸命、男の人に負けないように力を発揮して頑張っている。いじめられた自分が泣きながら帰っている途中、お母さんが子供のためにエンヤコラと働いている。そんな姿を見て、今度は涙を堪えて、「勉強するよ」と誓うのです。
ところで僕は石が大好きです。山や川、海に行くと石を探します。もしかしたら大切な文化財の一部かもしれないので、石を持って帰るときは注意をしますが、触ったり、握ったり、眺めてみたり。石っていろんなことを考えさせてくれるんですね。
山口さんは「穴太衆(あのうしゅう)」の話をしてくれた。
山口:京阪電車石山坂本線・終点の坂本比叡山口駅で降りると、正面に大きな看板が建っています。「世界文化遺産比叡山延暦寺」と「穴太衆積み門前町坂本」というもの。石を積むことを専門にした人がいらっしゃったところですね。

斜めになった土地を平にするために、石積みをして水田を作ります。日本国中の棚田はほとんどこうやって石積みをして、作られていましたが、この技術がさらに進化し、姫路城・大阪城・犬山城・岐阜城・松本城、そして江戸城の基礎を支える石垣が作り上げられました。作業したのが、坂本の穴太衆と呼ばれる方々だったのです。
この穴太衆は石を積み上げてドームを作ることができたそうだ。
山口:坂本の石垣を作る専門技術を持った人たちは、6世紀半ばから日本のほかの地域では見られない、古墳と横穴式石室を作っていました。石を積み上げてドームを作ることができた人たちなんです。
これはどういうことかと言うと、シベリアとかアラスカ、あるいはカナダ、グリーンランドのイヌイットの方々が氷の家「イグルー」を作るのと同じように、石を集めて型を整えてドームを作るのです。
それから韓国の伝統的な床暖房システム「オンドル」を、大きな石板を床下に敷いて作っていたことも確認されています。これらの技術が比叡山延暦寺の開山とともに山の上に持って行かれて、塔や石垣を作ることに応用されました。
坂本駅のそばには美しい石垣で囲まれた日本最古の茶園がある。
山口:この茶園の歴史を辿れば、唐へ留学した最澄が持ち帰ってきたお茶の種で育ったものだそうです。
最澄は空海の弟子でもありました。ですが「お前には才能がない!」と破門状受け取ることになります。そのとき、最澄は空海に対し「申し訳ありませんでした。私が悪かったです」と自分の非を詫びた手紙を送るときに、お茶を10斤(約6kg)送ったといわれています。

穴太衆が積む石垣の技術は世界でも非常に注目されています。米国・テキサス州のダラスにある「ロレックスタワー」。ものすごく大きな建物ですが、これを支えているのが穴太衆の人たちが積んだ石垣と言われています。
『ヨイトマケの唄』の歌詞を引用させてもらうなら<世界のためならエンヤコラ>といったところでしょうか。
ひとつひとつ石を積んでいく。人生も石垣のようなものなのかもしれませんね。みんな一生懸命、頑張りましょう!
(構成=中山洋平)
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。
関連リンク
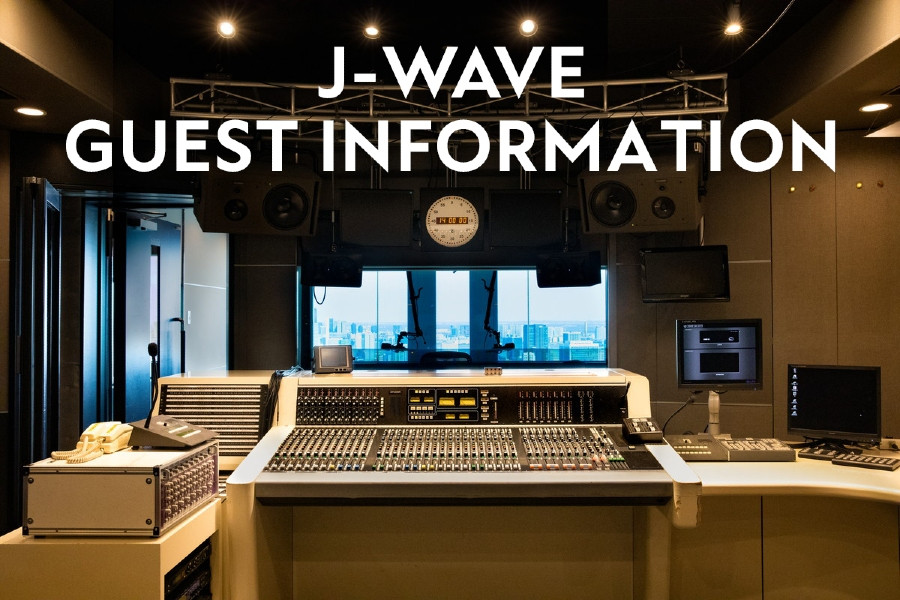 BMSG5周年特番、オダギリジョー、ノラ・ジョーンズ ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月19日(金)~9月26日(金)】
BMSG5周年特番、オダギリジョー、ノラ・ジョーンズ ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月19日(金)~9月26日(金)】 Jeep Wranglerの真の実力を体感! ピンクのWranglerが全国を巡回するキャラバンツアーを実施中
Jeep Wranglerの真の実力を体感! ピンクのWranglerが全国を巡回するキャラバンツアーを実施中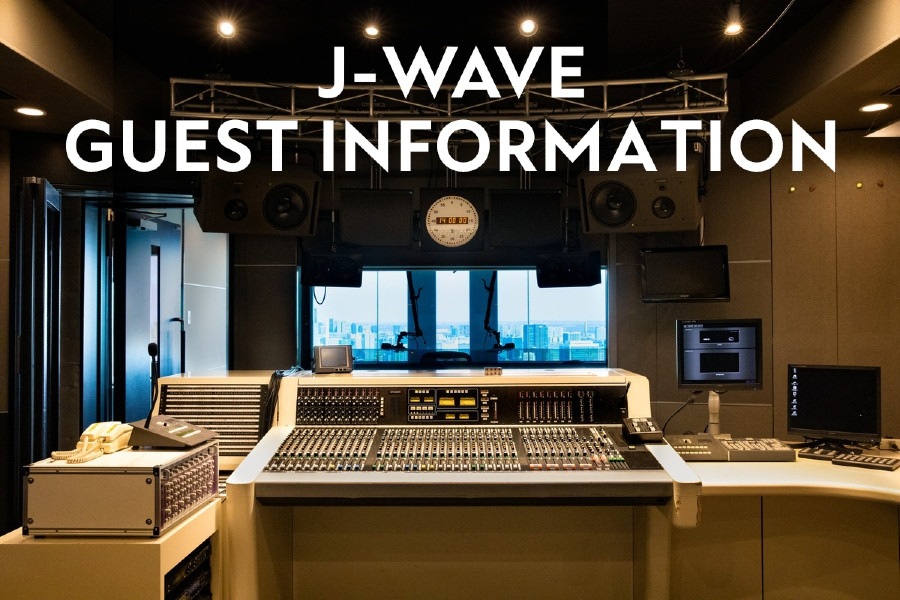 Chara、神尾楓珠、長嶋凛桜×池田瑛紗(乃木坂46) ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月12日(金)~9月19日(金)】
Chara、神尾楓珠、長嶋凛桜×池田瑛紗(乃木坂46) ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月12日(金)~9月19日(金)】 30周年「ラブシャ」ステージに立ったOmoinotake「ザ・パーフェクト黒ラベル」を片手にライブの感想と今後の展望語る
30周年「ラブシャ」ステージに立ったOmoinotake「ザ・パーフェクト黒ラベル」を片手にライブの感想と今後の展望語る SixTONES・ジェシー、suis from ヨルシカ、堀込泰行ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月5日(金)~9月12日(金)】
SixTONES・ジェシー、suis from ヨルシカ、堀込泰行ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月5日(金)~9月12日(金)】





