
提供:パナソニック株式会社
イヤホンを買うなら、いい音の製品がいい──音楽好きなら誰もが抱く想いだが、“いい音”の定義は意外と曖昧だ。「細部までクリアに聴こえる」「臨場感がある」などの条件が思い浮かびはするが、正解を教わる機会は一般人には少なく、自分が求めるものをリストアップすることは難しい。
いい音とは、いったいなんなのだろう? ここでは、「音づくりのプロ」と「音を鳴らす機材を作るプロ」へのインタビューから、ひとつの答えを考えていく。
 新井:僕たちの仕事を音楽制作に置き換えると、最終の仕上げである「マスタリング」に近いですね。簡単に言えば、音質や音量を聴きやすく調整してクオリティを高める工程です。例えばコンピレーションアルバムって、曲ごとにレコーディングされた状況は異なるのに、急に音が大きくなるなど音質面での聴き心地が大幅に変化することはありませんよね。これはマスタリングで均一化されているからなんです。
新井:僕たちの仕事を音楽制作に置き換えると、最終の仕上げである「マスタリング」に近いですね。簡単に言えば、音質や音量を聴きやすく調整してクオリティを高める工程です。例えばコンピレーションアルバムって、曲ごとにレコーディングされた状況は異なるのに、急に音が大きくなるなど音質面での聴き心地が大幅に変化することはありませんよね。これはマスタリングで均一化されているからなんです。
新井によると、放送の最終的な音質調整をする機材の設定項目は100以上もある。自分の耳で聴きながら理想の音になるよう調整していくそうだ。そんな技術者として思う、“いい音”の定義とは?
新井:ラジオにとってのいい音とは、アーティストが本当に伝えたい音=音源のニュアンスが損なわれておらず、なおかつリスナーが聴き疲れしないバランスの音だと思います。本音を言えば音源そのままの音を届けたいという気持ちもあるのですが、それは必ずしもリスナーにとっての“いい音”になるとは限りません。というのも、ラジオは媒体特性上、車の運転など何かをしながら楽しむリスナーもたくさんいらっしゃいます。もし、非常に繊細な音から始まるクラシックの名曲「Bolero」をそのまま流してしまったら、運転中のリスナーにとっては「曲が始まったら音がしなくなった」と、とらえられかねませんので、一般的にラジオでは、ある程度音量感を均一化する処理が必須なのです。また、ラジオは長時間流す方も多いため、聴き疲れしない音であることも重要です。こうしたバランスを追求した音が、J-WAVEが目指す“いい音”と言えます。
ヘッドホンやイヤホンなどの再生機器は「パワフルな印象にするため低音を強く」「高音を強調してキラキラさせる」などの“音の味付け”がされることもあるが、テクニクスの製品はそうした脚色をしていないことが特徴だそう。テクニクスのワイヤレスイヤホンの宣伝・プロモーションを担当する、パナソニック株式会社 デザイン本部 コミュニケーションデザインセンター クリエイティブ部 谷口泰星さんは、同ブランドが製品に込める“いい音”への想いをこう話す。
谷口:“いい音”というのは科学的、数値的には定義できず、各メーカーやブランドのこだわり、聞き手の好みで決まるものだと思います。テクニクスとしては、アーティストなどつくり手が一音、一音に込めた想い、エネルギー、空気感をそのまま届けることを重要視しており、脚色しない方向で製品の研究開発をしてきました。ワイヤレスイヤホンの最新フラグシップモデル「EAH-AZ80」も、これまで培ってきた技術を詰め込んで、アーティストの表現をありのまま届ける“いい音”を実現しています。
 特徴的な技術のひとつは、「アルミニウムの振動板」だ。ワイヤレスイヤホンの内部において振動板は、空気を揺らす役割を担っている。振動した空気がイヤーピースから鼓膜に届いて初めて人は音を知覚するのだ。一般的に用いられる樹脂振動板は空気の振動で大きくたわんでしまうため、音のひずみが発生しやすい。しかしアルミニウム振動板ならば、剛性の高さからたわみが少なく、正確な音が出せる。完全ワイヤレスイヤホン業界の中でも、「EAH-AZ80」に先んじて搭載されたのだそう。谷口さんによると、そのまっすぐな音は、コアなオーディオファンや、新井のような技術者からも好評を博しているそうだ。
特徴的な技術のひとつは、「アルミニウムの振動板」だ。ワイヤレスイヤホンの内部において振動板は、空気を揺らす役割を担っている。振動した空気がイヤーピースから鼓膜に届いて初めて人は音を知覚するのだ。一般的に用いられる樹脂振動板は空気の振動で大きくたわんでしまうため、音のひずみが発生しやすい。しかしアルミニウム振動板ならば、剛性の高さからたわみが少なく、正確な音が出せる。完全ワイヤレスイヤホン業界の中でも、「EAH-AZ80」に先んじて搭載されたのだそう。谷口さんによると、そのまっすぐな音は、コアなオーディオファンや、新井のような技術者からも好評を博しているそうだ。
 新井:僕は聴き手としても作り手としても、「空間を感じる音」がすごく好きなんです。「この音はどんな空間で、どんなふうに演奏されているんだろう?」と、目を閉じて映像が浮かんでくるような音に強く惹かれます。そういった意味において「EAH-AZ80」は、まさに空間をイメージさせるような音が響いているように思いました。
新井:僕は聴き手としても作り手としても、「空間を感じる音」がすごく好きなんです。「この音はどんな空間で、どんなふうに演奏されているんだろう?」と、目を閉じて映像が浮かんでくるような音に強く惹かれます。そういった意味において「EAH-AZ80」は、まさに空間をイメージさせるような音が響いているように思いました。
続けて「全帯域にわたって、過度な装飾のない、ありのままの上質な音が鳴っていると感じた」と体感を口にする。特に「よくできている」と感心したのは低音のクオリティだったという。
新井:ライブを生で観ると、ドン、ドンという低音が身体の芯に響くように感じますよね。あの感覚が「EAH-AZ80」から再生される低音でも味わえました。過去に観たライブで身体に記憶された振動の感覚が、ヘッドホンから流れる良い低音によって喚起されたことで起こっているのだと思います。ワイヤレスでも、無理に誇張した低音ではない、そのくらい実在感・リアリティのある、自分の知っている質の高い低音に近いニュアンスのローが出ていることに驚かされました。
 新井は、「EAH-AZ80」の聴き心地について、「これで音楽を聴くと楽しい」と述べる。利用したいシーンを訊くと……。
新井は、「EAH-AZ80」の聴き心地について、「これで音楽を聴くと楽しい」と述べる。利用したいシーンを訊くと……。
新井:我が家のリビングはちょっと高品質な据え置き型のスピーカーを設置しているのですが、早い時間に帰宅すると、大抵の場合は子どもたちに占拠されていて自由に音楽を聴くことができません(笑)。そんなときに、「EAH-AZ80」を装着して一人の世界に没入し、じっくりと好きな曲を楽しみたいですね。
アーティストたちによる演奏風景が浮かんでくるような空間を感じさせる音に、過去のライブで味わった振動がフラッシュバックするほどの低音……。こうしたリアルで臨場感のある音楽体験は、技術者がラジオ放送においてリスナーへの聴き心地を大切にしながらも最大限こだわる「原音」を、約60年間追求し続けたテクニクスの叡智と技術の結晶と言える。人の想像力を掻き立て、目を閉じれば、収録中のスタジオやライブ会場に連れて行ってくれるありのままの音こそが、“いい音”の一つの最適解なのかもしれない。
そんな発想からテクニクスでは、「あの場所で聴いていたあの曲は?」というエピソードを募るSNS投稿キャンペーンをはじめとする「忘れられない風景と音楽 プロジェクト」を2024年4月22日から5月31日まで実施。東京の駅構内ではポスター広告も展示した。
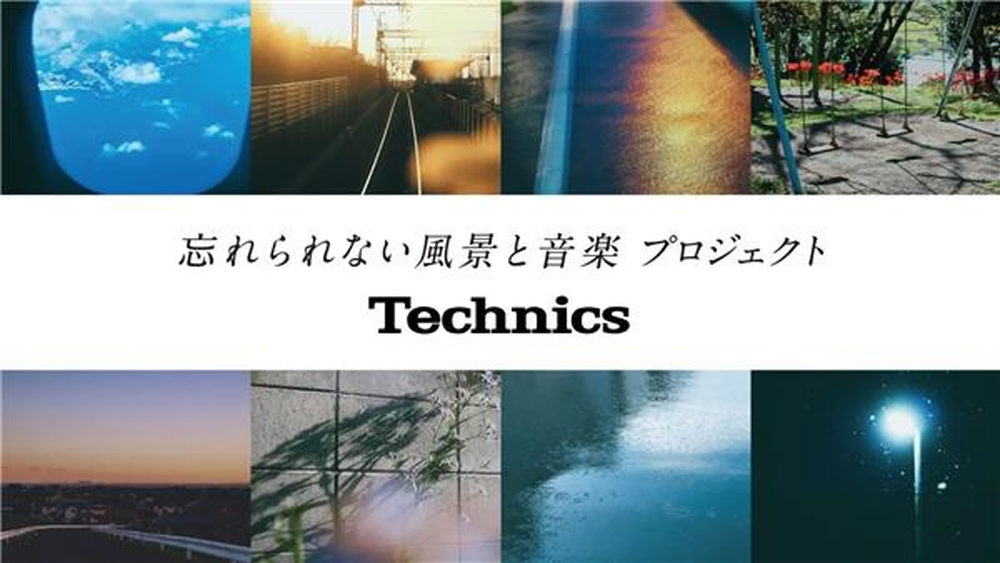
 谷口:ワイヤレスイヤホンには「いつでもどこでもいい音を楽しめる」という価値があります。また、音楽は、人生に寄り添ってくれるものですよね。そうしたメッセージを伝えるべく、新生活シーズンで多くの人が疲れやストレスを感じやすい春に、みんなでそれぞれの忘れられない風景と音楽に浸る本プロジェクトを企画しました。テクニクスは究極的に「人に感動を届けられる音」を目指しており、そのフィロソフィーを伝えることができればと思っています。
・「忘れられない風景と音楽 プロジェクト」詳細
谷口:ワイヤレスイヤホンには「いつでもどこでもいい音を楽しめる」という価値があります。また、音楽は、人生に寄り添ってくれるものですよね。そうしたメッセージを伝えるべく、新生活シーズンで多くの人が疲れやストレスを感じやすい春に、みんなでそれぞれの忘れられない風景と音楽に浸る本プロジェクトを企画しました。テクニクスは究極的に「人に感動を届けられる音」を目指しており、そのフィロソフィーを伝えることができればと思っています。
・「忘れられない風景と音楽 プロジェクト」詳細
https://jp.technics.com/products/tws/az80/fukeimusic/
最後に「テクニクスのイヤホンで、ユーザーにどんな価値を提供したいと考えているか」と質問すると、 谷口さんからはこんな答えが返ってきた。
谷口:テクニクスのブランドメッセージは「Rediscover Music.」。音楽の魅力や価値をまさに再発見していくことをブランドのひとつの存在意義としています。ワイヤレスイヤホンは、生活者にとってもっとも身近で手軽に手に入る音響機器の一つです。こだわりを持って選ぶことで好きなアーティストや楽曲の魅力を再発見することに繋がると思います。「EAH-AZ80」は、そういった体験の楽しさを向上させる製品だと自負しています。ご自身が聴いている音楽をこのイヤホンで聴いてどんな違いがあるのかを、ぜひ家電量販店の店頭や正規取扱店などで試してみてください。きっと、その価値が伝わるはずです。
(取材・文=小島浩平、撮影=竹内洋平)
・「EAH-AZ80」詳細
https://jp.technics.com/products/tws/az80/
イヤホンを買うなら、いい音の製品がいい──音楽好きなら誰もが抱く想いだが、“いい音”の定義は意外と曖昧だ。「細部までクリアに聴こえる」「臨場感がある」などの条件が思い浮かびはするが、正解を教わる機会は一般人には少なく、自分が求めるものをリストアップすることは難しい。
いい音とは、いったいなんなのだろう? ここでは、「音づくりのプロ」と「音を鳴らす機材を作るプロ」へのインタビューから、ひとつの答えを考えていく。
音づくりのプロが思う“いい音”とは?
まず“音づくりのプロ”として、J-WAVE NEWSの運営母体であるラジオ局・J-WAVEの技術者である新井康哲に話を聞いた。ナビゲーターがマイクに向かって話す「音の入り口」から、電波として発信される「音の出口」まで、ラジオ放送における音や機材の調整を行うのが新井をはじめとする技術者の仕事だ。その音は、緻密な調整がなされたうえでオンエアされている。音楽に力を入れていることから、他局と比較してライブ音源を扱うことも多いため、彼らによる音づくりはJ-WAVEらしさの根幹を担ってきた。
<新井康哲◎1998年J-WAVE入社以来、エンジニアとして数々のライブミックスを担当するほか、J-WAVEスタジオの音声システム設計や工事など、J-WAVEサウンドのコアを担う。主な実績:2014年COLD PLAY GHOST STORIESショーケースライブ全編ラジオ生中継ミックス、『SONAR MUSIC』『HELLO WORLD』などの一連の生放送スタジオライブミックス、「J-WAVE LIVE」「INSPIRE TOKYO」「TOKYO M.A.P.S」などJ-WAVE主催ライブイベントのラジオ放送用ミックス>
新井によると、放送の最終的な音質調整をする機材の設定項目は100以上もある。自分の耳で聴きながら理想の音になるよう調整していくそうだ。そんな技術者として思う、“いい音”の定義とは?
新井:ラジオにとってのいい音とは、アーティストが本当に伝えたい音=音源のニュアンスが損なわれておらず、なおかつリスナーが聴き疲れしないバランスの音だと思います。本音を言えば音源そのままの音を届けたいという気持ちもあるのですが、それは必ずしもリスナーにとっての“いい音”になるとは限りません。というのも、ラジオは媒体特性上、車の運転など何かをしながら楽しむリスナーもたくさんいらっしゃいます。もし、非常に繊細な音から始まるクラシックの名曲「Bolero」をそのまま流してしまったら、運転中のリスナーにとっては「曲が始まったら音がしなくなった」と、とらえられかねませんので、一般的にラジオでは、ある程度音量感を均一化する処理が必須なのです。また、ラジオは長時間流す方も多いため、聴き疲れしない音であることも重要です。こうしたバランスを追求した音が、J-WAVEが目指す“いい音”と言えます。
つくり手の想いを、ありのままに届けたい
次は、“音を鳴らす機材をつくるプロ”の意見を聞いていく。取材をしたのは、パナソニックのHi-Fi オーディオブランド Technics(テクニクス)だ。アンプやターンテーブルといったオーディオファン向けの製品から、ヘッドホンやイヤホンなど一般ユーザーが愛用できるアイテムまで幅広く展開する、60年の歴史を持つ日本ブランドだ。ヘッドホンやイヤホンなどの再生機器は「パワフルな印象にするため低音を強く」「高音を強調してキラキラさせる」などの“音の味付け”がされることもあるが、テクニクスの製品はそうした脚色をしていないことが特徴だそう。テクニクスのワイヤレスイヤホンの宣伝・プロモーションを担当する、パナソニック株式会社 デザイン本部 コミュニケーションデザインセンター クリエイティブ部 谷口泰星さんは、同ブランドが製品に込める“いい音”への想いをこう話す。
谷口:“いい音”というのは科学的、数値的には定義できず、各メーカーやブランドのこだわり、聞き手の好みで決まるものだと思います。テクニクスとしては、アーティストなどつくり手が一音、一音に込めた想い、エネルギー、空気感をそのまま届けることを重要視しており、脚色しない方向で製品の研究開発をしてきました。ワイヤレスイヤホンの最新フラグシップモデル「EAH-AZ80」も、これまで培ってきた技術を詰め込んで、アーティストの表現をありのまま届ける“いい音”を実現しています。

記憶を呼び覚ます、「空間を感じる音」
「EAH-AZ80」のキャッチコピーは、「ワイヤレスでも、高音質をあきらめない」。実際、これまで有線イヤホンを愛用していたユーザーからも「ここまで有線の音質に近づいているんだ」という驚きの声が多数寄せられているそうだ。では、仕事でプロ仕様の有線ヘッドホンを用いる新井の耳には、「EAH-AZ80」の音はどう聴こえたのか? 試聴後に感想を尋ねてみた。
続けて「全帯域にわたって、過度な装飾のない、ありのままの上質な音が鳴っていると感じた」と体感を口にする。特に「よくできている」と感心したのは低音のクオリティだったという。
新井:ライブを生で観ると、ドン、ドンという低音が身体の芯に響くように感じますよね。あの感覚が「EAH-AZ80」から再生される低音でも味わえました。過去に観たライブで身体に記憶された振動の感覚が、ヘッドホンから流れる良い低音によって喚起されたことで起こっているのだと思います。ワイヤレスでも、無理に誇張した低音ではない、そのくらい実在感・リアリティのある、自分の知っている質の高い低音に近いニュアンスのローが出ていることに驚かされました。

新井:我が家のリビングはちょっと高品質な据え置き型のスピーカーを設置しているのですが、早い時間に帰宅すると、大抵の場合は子どもたちに占拠されていて自由に音楽を聴くことができません(笑)。そんなときに、「EAH-AZ80」を装着して一人の世界に没入し、じっくりと好きな曲を楽しみたいですね。
アーティストたちによる演奏風景が浮かんでくるような空間を感じさせる音に、過去のライブで味わった振動がフラッシュバックするほどの低音……。こうしたリアルで臨場感のある音楽体験は、技術者がラジオ放送においてリスナーへの聴き心地を大切にしながらも最大限こだわる「原音」を、約60年間追求し続けたテクニクスの叡智と技術の結晶と言える。人の想像力を掻き立て、目を閉じれば、収録中のスタジオやライブ会場に連れて行ってくれるありのままの音こそが、“いい音”の一つの最適解なのかもしれない。
音楽体験が人生を彩っていく
音楽を楽しむということは、「学校からの帰り道で聴いていた」といったシチュエーションや、「失恋したときに励まされた」などのパーソナルなエピソードと密接に繋がっている。“いい音”で楽しむことができれば、そうした音楽体験はより上質なものになる。その意味で、外出先で役立つワイヤレスイヤホンは重要なアイテムと言えるだろう。そんな発想からテクニクスでは、「あの場所で聴いていたあの曲は?」というエピソードを募るSNS投稿キャンペーンをはじめとする「忘れられない風景と音楽 プロジェクト」を2024年4月22日から5月31日まで実施。東京の駅構内ではポスター広告も展示した。
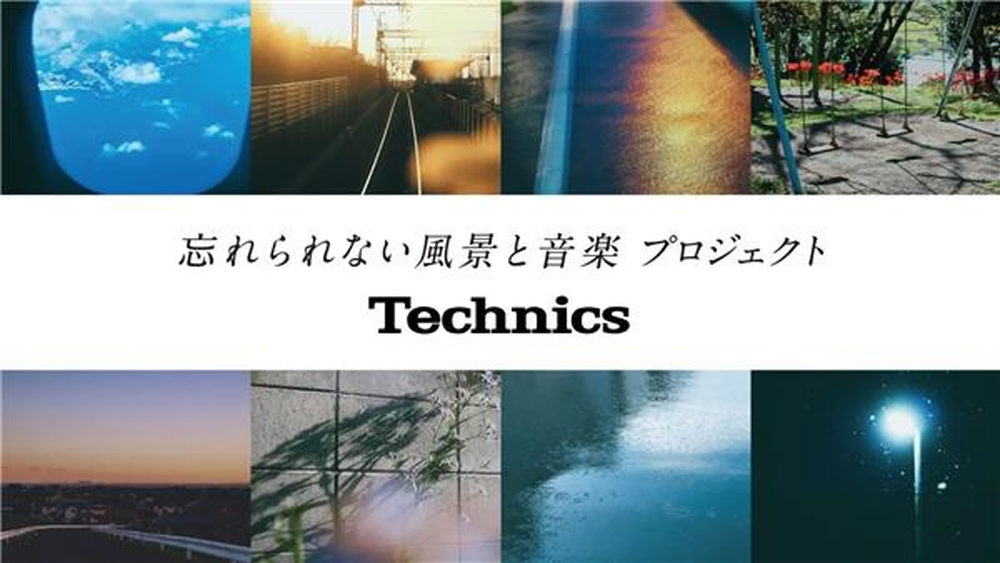
<思い出の音楽を聴くことで当時の風景と記憶を再生し、自分自身の心を再生することを目指して発足した「忘れられない風景と音楽 プロジェクト」。SNS投稿キャンペーンのほか、コンセプトムービーの公開、および音声広告を配信。リーガルリリーのたかはしほのか、歌人の木下龍也がナレーションを務めるほか、YouTubeチャンネルの総再生回数8,000万回を超えるマルチクリエイターの深根が書き下ろした新曲「あの空とおく」を起用した>

[Technics AZ80]忘れられない風景と音楽「2つの物語/A面」【テクニクス公式】
[Technics AZ80]忘れられない風景と音楽「2つの物語/B面」【テクニクス公式】
https://jp.technics.com/products/tws/az80/fukeimusic/
最後に「テクニクスのイヤホンで、ユーザーにどんな価値を提供したいと考えているか」と質問すると、 谷口さんからはこんな答えが返ってきた。
谷口:テクニクスのブランドメッセージは「Rediscover Music.」。音楽の魅力や価値をまさに再発見していくことをブランドのひとつの存在意義としています。ワイヤレスイヤホンは、生活者にとってもっとも身近で手軽に手に入る音響機器の一つです。こだわりを持って選ぶことで好きなアーティストや楽曲の魅力を再発見することに繋がると思います。「EAH-AZ80」は、そういった体験の楽しさを向上させる製品だと自負しています。ご自身が聴いている音楽をこのイヤホンで聴いてどんな違いがあるのかを、ぜひ家電量販店の店頭や正規取扱店などで試してみてください。きっと、その価値が伝わるはずです。
(取材・文=小島浩平、撮影=竹内洋平)
・「EAH-AZ80」詳細
https://jp.technics.com/products/tws/az80/
この記事の続きを読むには、
以下から登録/ログインをしてください。





